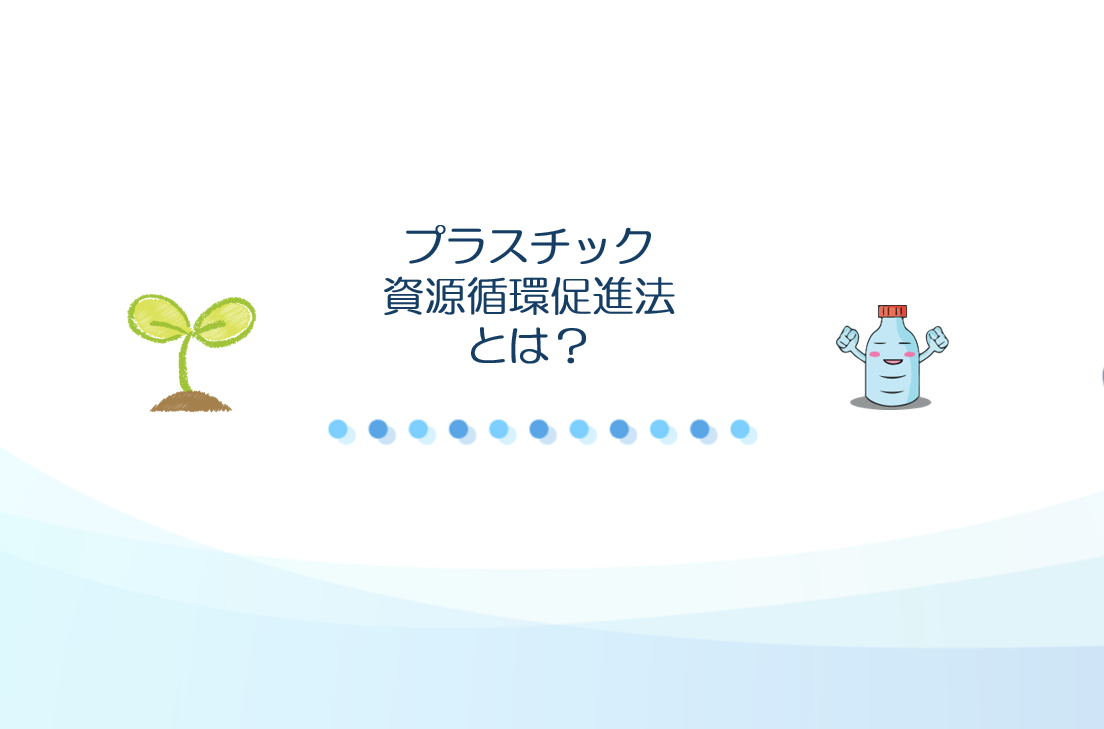皆さんこんにちは。都市環境サービスの前田です。今回のテーマは「プラスチック資源循環促進法」です。コンビニでもらうスプーンやホテルのアメニティが有料化されたり、プラスチック製品が環境に配慮したものに変わってきたりと、最近身の回りで変化を感じている方も多いのではないでしょうか。

実は2022年4月から「プラスチック資源循環促進法」という新しい法律が施行されているんです。この法律は、企業や自治体、そして私たち消費者が協力してプラスチックごみを減らし、資源として循環させることを目指しています。でも、具体的に何が変わったのか、どんな製品が対象なのか、よくわからないという声も多く聞かれます。
目次は以下の通りです。
① 法律の基本情報
② 3R+Renewableとは
③ 対象となる12品目
④ 企業に求められること
⑤ 対象事業者の基準
⑥ 罰則について
⑦ 企業の具体的な取組
⑧ 環境配慮設計
⑨ 自主回収制度
⑩ 今後の展望
プラスチック資源循環促進法は、私たちの生活や企業活動に大きく関わる重要な法律なんです。環境問題への対応や、これからの社会のあり方を知るためにも、ぜひ最後までご一読ください。
法律の基本情報
プラスチック資源循環促進法がなぜ必要になったのか、そしてこの法律が目指す社会について、まずは基礎知識を押さえていきましょう。
施行の背景
プラスチック資源循環促進法が制定された背景には、深刻化する環境問題があります。世界中で年間800万トンを超えるプラスチックが海洋に流出しており、海洋生物の生態系に大きな被害を与えているんです。
特に問題となっているのが「海洋プラスチックごみ」です。太平洋にはアメリカ大陸とハワイの間に「太平洋ごみベルト」と呼ばれる巨大なごみの塊が存在しています。その面積は約160万平方キロメートルで、日本の国土の4倍以上にもなるんですよ。
また、プラスチックは石油を原料としているため、製造時や焼却時に温室効果ガスが発生します。気候変動問題への対応も急務となっており、2019年5月に政府が「プラスチック資源循環戦略」を策定したことが、この法律制定のきっかけになりました。
法律の目的
プラスチック資源循環促進法の正式名称は「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」といいます。2022年4月1日に施行されたこの法律は、プラスチック製品の設計から廃棄物の処理まで、すべての段階で資源循環を促進することを目的としています。
この法律が目指すのは「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」への移行です。サーキュラーエコノミーとは、製品や資源を廃棄せずに何度も循環させて使う経済の仕組みのことなんです。使い捨てではなく、資源を大切に使い続ける社会を実現しようとしています。
具体的には、事業者、自治体、消費者が連携しながら、プラスチックの排出抑制と再資源化に取り組みます。環境・経済・社会の三方よしな社会を目指しているんですよ。

3R+Renewableとは
プラスチック資源循環促進法の基本原則である「3R+Renewable」について、それぞれの取り組み内容を詳しく見ていきます。
Reduceの取り組み
Reduce(リデュース)とは、プラスチック製品の使用量そのものを減らすことを指します。ごみの発生を元から抑えることが最も重要なんです。
具体的には、製品の設計段階からプラスチックの使用量を削減する工夫が求められています。例えば、ペットボトルの軽量化や薄肉化、包装材の簡易化などが該当します。2022年にはウィンナーの包装が巾着型から封筒型に変更され、使用するプラスチック量が大幅に削減されました。
また、私たち消費者も過剰な包装を避けたり、不要なプラスチック製品をもらわないようにしたりすることで、Reduceに貢献できます。レジ袋の有料化も、この取り組みの一環なんですよ。
Reuseの取り組み
Reuse(リユース)とは、プラスチック製品を繰り返し使用することを意味します。使い捨てを減らし、同じ製品を何度も使うことで廃棄物の発生を抑えることができるんです。
身近な例としては、マイバッグやマイボトルの使用があります。買い物のたびに新しいレジ袋をもらうのではなく、自分のバッグを持参することで、プラスチックの消費を大幅に削減できます。
企業の取り組みとしては、詰め替え用製品の販売や、容器の回収・再利用システムの構築などが進められています。ボールペンも芯を交換できるタイプにすることで、本体を長く使い続けることができるようになっています。
Recycleの取り組み
Recycle(リサイクル)とは、廃棄されたプラスチック製品を資源として再生利用することです。日本の廃プラスチックの有効再利用率は85%を超えており、世界的に見ても高い水準を達成しています。
リサイクルには、プラスチックを溶かして新しい製品に作り替える「マテリアルリサイクル」と、化学的に分解して原料に戻す「ケミカルリサイクル」などがあります。ペットボトルをペットボトルに再生する取り組みも進んでおり、資源の循環が実現されているんです。
ただし、リサイクルを効率的に行うためには、適切な分別が不可欠です。プラスチックには多様な種類があり、それぞれリサイクル方法が異なるため、正しく分別することが重要なんですよ。
リサイクルの種類について詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。
Renewableの取り組み
Renewable(リニューアブル)とは、再生可能な資源に切り替えることを意味します。従来の石油由来のプラスチックから、環境に優しい素材への転換を目指しているんです。
代表的なのが「バイオマスプラスチック」です。これは植物などの再生可能な原料から作られるプラスチックで、微生物によって分解されるものもあります。トウモロコシやサトウキビから作られるため、石油資源の消費を抑えることができるんですよ。
日本政府は2030年までにバイオマスプラスチックを約200万トン導入する目標を掲げています。レジ袋をバイオマスプラスチック製に切り替える動きも広がっており、今後さらに普及が進むと期待されています。
3Rについて詳しく知りたい方は下記をご覧ください。

対象となる12品目
プラスチック資源循環促進法では、特に削減が求められる「特定プラスチック使用製品」として12品目が指定されています。業種ごとに見ていきましょう。
飲食店向けの品目
飲食店やコンビニエンスストアで提供される使い捨てプラスチック製品が対象となっています。私たちが日常的に目にする製品ばかりなんです。
飲食店向けの対象品目は以下になります。
1.フォーク
2.スプーン
3.ナイフ
4.マドラー
5.ストロー
これらは商品の販売や飲食サービスに付随して、消費者に無償で提供されるプラスチック製品です。お弁当を買ったときにもらうスプーンや、ドリンクに付いてくるストローなどが該当します。
年間5トン以上これらの製品を提供する事業者は、有償化や必要な人にだけ渡すなどの合理化措置を講じる必要があります。コンビニ大手では、既に「スプーンが必要ですか」と確認する対応が始まっているんですよ。
宿泊施設向けの品目
ホテルや旅館などの宿泊施設で提供されるアメニティグッズも、削減対象となっています。無料で部屋に置かれている使い捨て製品が該当するんです。
宿泊施設向けの対象品目は以下になります。
6.ヘアブラシ
7.くし
8.カミソリ
9.シャワーキャップ
10.歯ブラシ
これらのアメニティは、一度使われただけで廃棄されることが多く、大量のプラスチックごみを生み出していました。そのため、宿泊施設には提供方法の見直しが求められています。
最近では、必要な人だけがフロントで受け取る方式に変更したり、環境に配慮した素材のアメニティに切り替えたりするホテルが増えています。
小売店向けの品目
クリーニング店などで使用されるプラスチック製品も対象となっています。衣類の保管や持ち帰りに使われる製品が該当するんです。
小売店向けの対象品目は以下になります。
11.ハンガー
12.衣類用カバー
クリーニングから戻ってきた衣類に付いているハンガーやビニールカバーは、多くの場合すぐに外されて捨てられています。これらも大量のプラスチックごみとなっているため、削減対象に指定されました。
クリーニング店では、ハンガーの回収・再利用システムを導入したり、紙製のカバーに切り替えたりする取り組みが進められています。
企業に求められること
プラスチック資源循環促進法では、企業の立場によって異なる取り組みが求められています。それぞれの役割を確認していきましょう。
設計・製造業者
プラスチック製品を設計・製造する事業者には、環境に配慮した製品作りが求められています。製品が生まれる最初の段階から、資源循環を意識することが重要なんです。
国が策定した「プラスチック使用製品設計指針」に沿って、製品の設計を行う必要があります。具体的には、プラスチックの使用量削減、部品の再使用、リサイクルしやすい設計、代替素材の利用、再生プラスチックやバイオマスプラスチックの活用などが求められています。
この指針に適合すると認定された製品は、製造設備への支援が受けられたり、国による物資調達の対象となったりするメリットがあります。現時点では罰則はありませんが、環境配慮は企業の社会的責任として重要視されているんです。
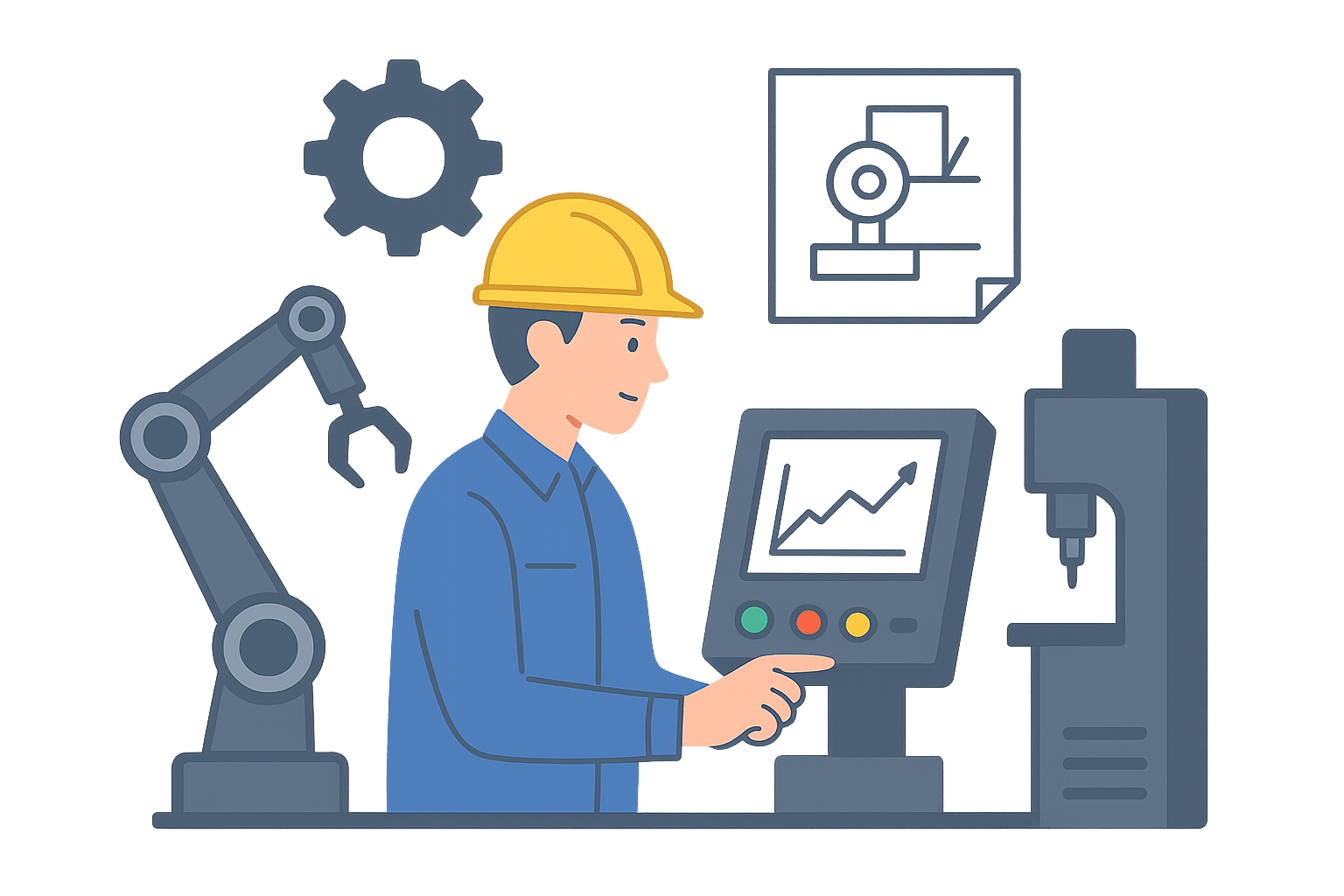
販売・提供業者
コンビニやスーパー、飲食店、宿泊施設など、12品目の特定プラスチック使用製品を提供する事業者には、使用の合理化が求められています。無償で配っていた製品の提供方法を見直す必要があるんです。
合理化の方法としては、有償での提供、ポイント還元などのインセンティブ付与、必要性を確認してからの提供、繰り返し使える製品への転換、軽量化や代替素材への変更などがあります。
年間5トン以上の特定プラスチック使用製品を提供する多量提供事業者には、主務大臣から勧告を受ける可能性があります。勧告に従わない場合は企業名が公表され、さらに命令にも従わなければ罰則が科されることもあるんですよ。

排出事業者
プラスチック廃棄物を排出する事業者には、排出抑制と再資源化の取り組みが求められています。オフィスや工場、店舗などで発生するプラスチックごみを減らし、リサイクルに回す努力が必要なんです。
年間250トン以上のプラスチック使用製品産業廃棄物を排出する多量排出事業者には、より厳しい義務が課されています。排出の抑制・再資源化の目標を設定し、その達成状況や取り組み内容をインターネットなどで公表することが求められているんです。
社内書類の電子化によるプラスチック製バインダーの使用削減や、資料を渡す際のプラスチック製クリアファイルの削減なども、有効な取り組みとして推奨されています。

対象事業者の基準
プラスチック資源循環促進法では、排出量や提供量に応じて対象事業者が定められています。具体的な基準を確認していきましょう。
年間5トン以上
特定プラスチック使用製品の12品目を年間5トン以上提供する事業者は「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」として、使用の合理化に取り組む義務があります。大手のコンビニチェーン、スーパー、飲食店、ホテルなどが該当するんです。
5トンという数字は、例えばプラスチック製スプーン1本を約5グラムとすると、年間100万本に相当します。大規模な店舗や多店舗展開している企業であれば、この基準に達する可能性が高いんですよ。
これらの事業者は、取り組みが著しく不十分な場合、主務大臣から勧告を受けることがあります。勧告を受けても措置を講じない場合は、企業名の公表や命令が行われ、最終的には50万円以下の罰金が科される可能性もあります。
年間250トン以上
プラスチック使用製品産業廃棄物を年間250トン以上排出する事業者は「プラスチック使用製品産業廃棄物等多量排出事業者」として、より詳細な取り組みが義務付けられています。製造業や大規模オフィスなどが対象となるケースが多いんです。
これらの事業者には、排出抑制や再資源化に関する判断基準が設けられています。具体的には、プラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制、分別、再資源化などに取り組む必要があります。
さらに重要なのが、目標設定と情報公表の義務です。前年度の排出量、排出抑制・再資源化の目標、取り組み内容とその効果などを、自社のウェブサイトなどで公表することが求められています。こうした透明性の確保も、法律の重要な要素なんですよ。
罰則について
プラスチック資源循環促進法における罰則の仕組みを理解しておくことは、企業にとって重要です。どのような場合に罰則が適用されるのか見ていきましょう。
努力義務の内容
プラスチック資源循環促進法で企業に求められる多くの取り組みは「努力義務」として位置付けられています。努力義務とは、法律で定められた行動を「努めなければならない」というもので、即座に罰則が適用されるわけではないんです。
例えば、設計・製造段階での環境配慮設計や、一般的な排出事業者の排出抑制・再資源化の取り組みは努力義務です。法律に従わなかったからといって、すぐに罰金を支払う必要はありません。
しかし、努力義務だからといって無視してよいわけではありません。環境問題への取り組みは企業の社会的責任として重要視されており、対応が遅れると企業イメージの低下や、取引先からの信頼を失うリスクがあるんですよ。
勧告から罰金まで
特定の事業者に対しては、段階的な行政指導を経て、最終的に罰則が適用される仕組みになっています。いきなり罰金が科されるわけではなく、改善の機会が与えられるんです。
罰則適用までの流れは以下になります。
取り組みが不十分
主務大臣からの勧告
企業名の公表
主務大臣からの命令
50万円以下の罰金
具体的には、年間5トン以上の特定プラスチック使用製品を提供する事業者や、年間250トン以上のプラスチック廃棄物を排出する事業者が、著しく取り組みが不十分な場合に勧告を受けます。勧告を受けても措置を講じなければ企業名が公表され、さらに命令にも従わない場合に罰金が科されます。
企業にとって、罰金以上に深刻なのが「企業名の公表」です。環境問題への対応が不十分だと公表されることは、ブランドイメージを大きく損なうリスクがあるため、多くの企業が自主的に取り組みを進めているんです。
企業の具体的な取組
実際に企業がどのような取り組みを行っているのか、具体的な事例を業種別に紹介していきます。
コンビニの事例
コンビニエンスストア各社は、プラスチック資源循環促進法の施行に先駆けて、様々な取り組みを開始しています。消費者との接点が多い業態だけに、積極的な対応が求められているんです。
大手コンビニチェーンでは、カトラリー類の提供方法を見直しています。レジで「スプーンやフォークは必要ですか」と確認し、必要な人にだけ渡すようにすることで、無駄な提供を削減しました。また、カトラリーを木製や紙製に切り替える動きも広がっています。
さらに、ポイント還元システムを導入している店舗もあります。カトラリーを辞退した顧客にポイントを付与することで、環境配慮行動を促進しているんですよ。こうした取り組みにより、プラスチック使用量の大幅な削減に成功しています。
ホテルの事例
宿泊業界でも、アメニティの提供方法を大きく見直す動きが広がっています。客室に当たり前のように置かれていた使い捨てアメニティが、環境配慮の観点から変化しているんです。
多くのホテルチェーンでは、歯ブラシやカミソリなどのアメニティを客室から撤去し、必要な人だけがフロントで受け取るシステムに変更しました。また、プラスチック製から生分解性プラスチックやバイオマスプラスチック製への切り替えも進んでいます。
さらに先進的な取り組みとして、ストローを紙製に変更したり、ヘアブラシを竹製にしたりするホテルも登場しています。宿泊客の環境意識も高まっており、こうした取り組みが宿泊施設選びの判断材料になることも増えているんですよ。
メーカーの事例
製造業では、製品設計の段階からプラスチック削減に取り組む企業が増えています。ライフサイクル全体を見据えた環境配慮が重要視されているんです。
飲料メーカーでは、ペットボトルの軽量化や薄肉化を進めています。ラベルを小さくしたり、ラベルレス商品を販売したりすることで、プラスチック使用量を削減しました。また、ペットボトルをペットボトルに再生する「ボトルtoボトル」の取り組みも拡大しています。
食品メーカーでは、包装材の見直しが進んでいます。ウィンナーの包装を巾着型から封筒型に変更し、プラスチック使用量を約20%削減した事例や、詰め替え用製品の充実により容器の再利用を促進している事例などがあります。こうした取り組みは、環境負荷を減らすだけでなく、企業のブランド価値向上にもつながっているんです。
環境配慮設計
プラスチック製品の設計段階から環境に配慮することが、資源循環を実現する鍵となります。具体的な設計の工夫を見ていきましょう。
単一素材化
単一素材化とは、製品を一種類の素材だけで作ることです。リサイクルの効率を大幅に向上させることができるんですよ。従来のペットボトルは、本体とラベルが異なる素材で作られていたため、リサイクルする際には分離する必要がありました。
しかし、本体もラベルも同じPET素材で作れば、分離せずにそのままリサイクルに出せます。消費者の手間も減り、リサイクル施設での処理も効率化されるんです。
調味料のボトルなども、単一素材化が進んでいます。本体、キャップ、ラベルをすべて同じ素材にすることで、分別の手間を省きながら高品質なリサイクルを実現しています。単一素材化は、製品設計における重要な環境配慮の手法として広まっているんですよ。
分離の容易化
どうしても複数の素材を使う必要がある場合は、簡単に分離できるような設計が求められています。リサイクル時の作業負担を減らすことが目的なんです。
最近の調味料ボトルでは、キャップを簡単に外せる構造になっています。従来は固く閉まっていて外しにくかったキャップが、手で簡単に分離できるように改良されました。また、ラベルにミシン目を入れて、手で簡単に剥がせるようにした製品も増えています。
食品トレイでも、フィルムと本体を簡単に分離できる設計が採用されています。消費者が無理なく分別できることで、リサイクル率の向上につながるんです。分離の容易化は、製品の使いやすさを保ちながら環境配慮を実現する、優れた設計手法といえます。
軽量化の工夫
製品を軽くすることで、使用するプラスチックの量を減らすことができます。Reduce(削減)の取り組みとして、多くの企業が軽量化に挑戦しているんです。
ペットボトルは、この20年間で大幅な軽量化が進みました。技術革新により、強度を保ちながら薄くすることが可能になり、2リットルボトルでは約30%の軽量化を実現した製品もあります。運搬時の環境負荷も減らせるため、CO2削減効果も大きいんですよ。
レジ袋も、薄肉化技術の向上により、従来より薄くても破れにくい製品が開発されています。食品トレイやカップ麺の容器なども、必要な強度を確保しながら薄くする工夫が続けられています。軽量化は、資源節約とコスト削減を同時に実現できる、企業にとってもメリットの大きい取り組みなんです。
自主回収制度
プラスチック資源循環促進法には、製造・販売事業者が自主的に製品を回収してリサイクルする仕組みが設けられています。この制度について詳しく見ていきましょう。
認定制度の概要
「自主回収・再資源化事業計画認定制度」とは、製造・販売事業者が使用済みのプラスチック製品を回収し、リサイクルする計画を国が認定する制度です。認定を受けると、廃棄物処理法に基づく業の許可が不要になるメリットがあるんです。
この制度は、プラスチックのリサイクル拡大・促進を目的としています。店頭回収などで消費者から自社製品を回収し、リサイクルして新しい製品に生まれ変わらせる循環の仕組みを作るんですよ。
認定を受けるには、回収方法、運搬方法、再資源化方法などを含む事業計画を作成し、環境省や経済産業省に申請する必要があります。計画が適切だと認められれば、通常は必要な廃棄物処理業の許可なしに、回収・リサイクル事業を実施できるようになります。
申請の流れ
自主回収・再資源化事業計画の認定を受けるためには、いくつかの手順を踏む必要があります。計画的に準備を進めることが重要なんです。
まず、使用済み製品の回収体制を構築します。店舗での回収ボックス設置や、消費者への情報発信方法などを具体的に計画します。次に、回収した製品をどのように運搬し、どのような方法でリサイクルするかを決定します。
その後、これらの内容を盛り込んだ事業計画書を作成し、主務大臣に申請します。計画の実現可能性や環境への配慮、リサイクルの効率性などが審査され、基準を満たしていれば認定を受けられます。認定後は、計画に沿って事業を実施し、定期的に実施状況を報告することが求められるんですよ。
まとめ
プラスチック資源循環促進法は、私たちの生活と環境を守るための重要な法律です。コンビニでスプーンを辞退する、マイバッグを使う、正しく分別するといった小さな行動が、海洋汚染の防止や気候変動対策につながっています。
企業には環境配慮設計や使い捨て製品の削減が求められ、私たち消費者にもプラスチックとの向き合い方を見直すことが期待されています。2030年の目標達成、そして持続可能な社会の実現に向けて、一人ひとりができることから始めてみませんか。環境問題は遠い話ではなく、今日からの行動で未来が変わる身近な課題なのです。
お知らせ
最後まで、読んでいただき光栄です。私たち都市環境サービスは、プラスチックリサイクルに特化した会社です。フラフ燃料の製造や代替燃料に興味がある方、リサイクルの会社で働いてみたい方は、こちらのフォームから気軽にお問合せください。よろしくお願いします。