皆さんこんにちは。都市環境サービスの前田です。今回のテーマは「マイクロプラスチック問題」です。普段使っているペットボトルや洗顔料、実はそれらが見えないほど小さな粒子となって環境や私たちの体に影響を与えていることをご存知でしょうか?

実は、マイクロプラスチックは既に世界中の海に広がり、魚や貝などの海洋生物の体内から検出されているんです。そして驚くことに、私たち人間の血液や内臓からも発見されているんですよ。これは決して遠い国の話ではなく、私たちの身近な問題なんです。
本記事では、マイクロプラスチック問題について、その正体から人体への影響、そして今日からできる対策まで詳しく解説していきます。
目次は以下の通りです。
①マイクロプラスチックの基本知識
②マイクロプラスチックの発生源
③海洋生物への深刻な影響
④人体への影響と健康リスク
⑤日本の深刻な汚染状況
⑥効果的な対策と解決策
⑦未来への課題と展望
マイクロプラスチック問題は私たちの健康と地球環境に直結する重要な課題です。ぜひ最後までお読みください。
マイクロプラスチック問題とは
マイクロプラスチック問題とは、直径5ミリメートル以下の微小なプラスチック粒子が環境中に拡散し、生態系や人間の健康に影響を与える深刻な環境問題なんです。この問題が注目されるようになったのは2000年代からですが、実際には1970年代から海洋中での存在が確認されていました。
現在、世界全体で年間800万トンを超えるプラスチックごみが海洋に流出していると推計されています[1]。その中でも特に問題となっているのが、マイクロプラスチックです。これらの微小な粒子は、一度環境中に放出されると回収が極めて困難で、数百年から数千年にわたって自然界に残存し続けます。
マイクロプラスチックは、肉眼では見えないほど小さいため「見えない汚染」と呼ばれることもあります。しかし、その影響は決して小さくありません。海洋生物が餌と間違えて摂取し、食物連鎖を通じて濃縮されることで、最終的に私たち人間の食卓にも届いているのが現状です。
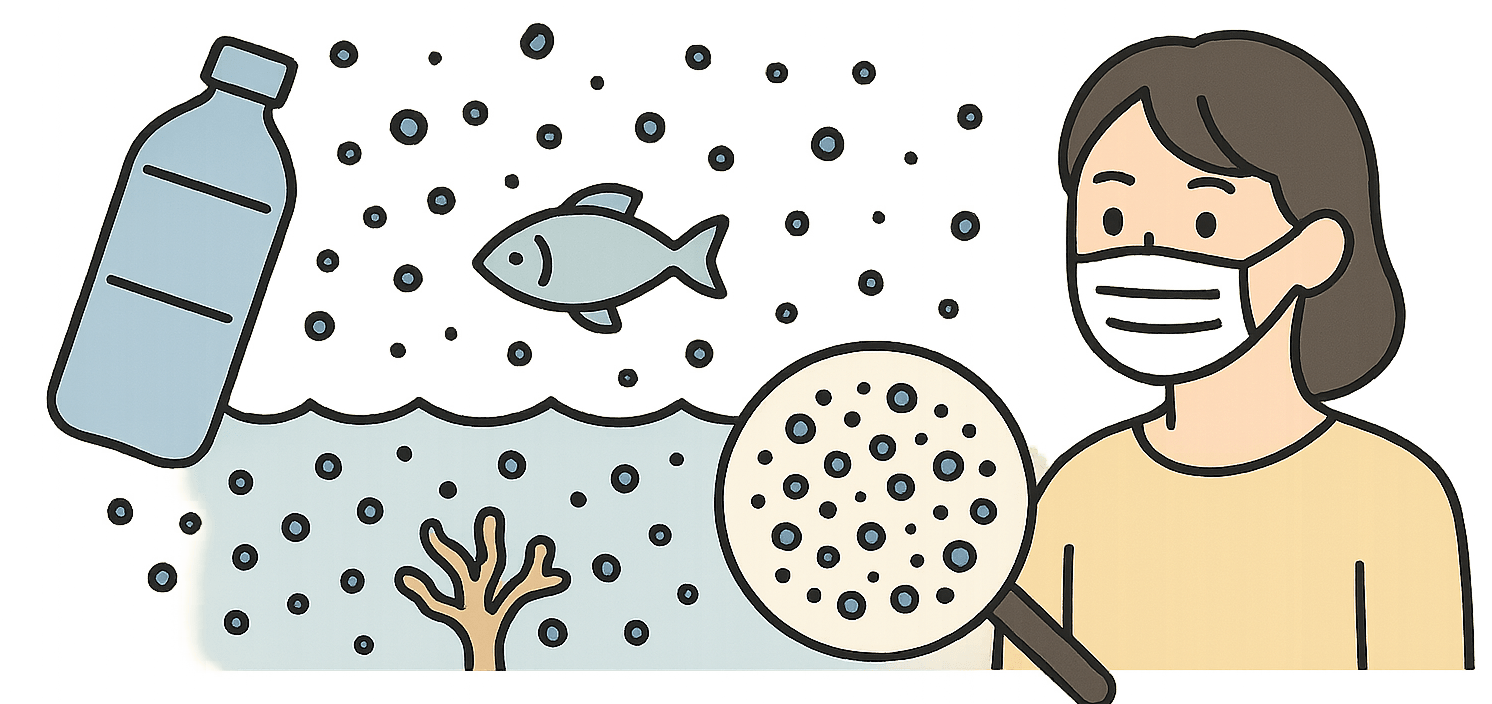
マイクロプラスチックの基本知識
マイクロプラスチックについて詳しく理解するために、その定義と種類について説明していきます。
5mm以下の見えない汚染物質
マイクロプラスチックとは、大きさが5ミリメートル以下のプラスチック粒子のことです。5ミリメートルがどのくらいの大きさかというと、ちょうど5円玉の穴の直径と同じくらいです。実際にはもっと小さなものが多く、1ミリメートル以下のものがほとんどを占めています。
さらに小さなものでは、1000分の1ミリメートル(1マイクロメートル)以下の「ナノプラスチック」と呼ばれるものもあります。これらは顕微鏡でも見えないほど小さく、空気中にも漂っているんです。
マイクロプラスチックの見た目は様々で、透明なもの、白いもの、カラフルなものなど多種多様です。形状も球状、繊維状、破片状など異なります。材質も、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリエチレンテレフタレート(PET)など、私たちが日常的に使用するプラスチック製品と同じものです。
2つの発生タイプとは
マイクロプラスチックは、発生の仕方によって2つのタイプに分類されます。
一次マイクロプラスチックは、最初から小さなサイズで製造されたプラスチック粒子です。代表的なものには、洗顔料やスクラブ剤に含まれる「マイクロビーズ」、プラスチック製品の原料となる「樹脂ペレット」があります。これらは製造段階ですでに微小なサイズになっているため、使用後に直接環境中に放出されます。
二次マイクロプラスチックは、元々大きなプラスチック製品が環境中で劣化・破砕されて小さくなったものです。ペットボトル、レジ袋、食品容器などが紫外線や波の力、物理的な摩擦によって徐々に細かくなっていきます。また、合成繊維の衣類を洗濯した際に出る繊維くずも、この二次マイクロプラスチックに含まれます。
現在、海洋に流出するマイクロプラスチックの大部分は二次マイクロプラスチックが占めており、適切な廃棄物管理の重要性が指摘されているんですよ。
マイクロプラスチックの発生源
私たちの身の回りには、マイクロプラスチックを生み出す様々な発生源が存在しています。
日用品から生まれる一次汚染
一次マイクロプラスチックの主な発生源となる日用品は以下になります。
洗顔料・歯磨き粉
・スクラブ剤
・マイクロビーズ
・研磨剤成分
日用品からの直接流出
洗顔料や歯磨き粉に含まれるマイクロビーズは、洗い流す際に排水溝から下水処理場に送られます。しかし、その小ささゆえに完全に除去することは困難で、一部は処理されずに海に流出してしまいます。近年、多くのメーカーがマイクロビーズの使用を中止していますが、完全になくなったわけではありません。
化粧品では、ファンデーションやコンシーラー、チークなどにもマイクロプラスチックが使用されている場合があります。これらは肌に塗った後、洗顔時に除去され、同様に環境中に放出される可能性があるんです。
また、プラスチック製品の原料となる樹脂ペレット(レジンペレット)の流出も深刻な問題です。製造工場や運搬過程での事故により、大量のペレットが環境中に放出される事例が世界各地で報告されています。
劣化で生まれる二次汚染
二次マイクロプラスチックの発生源は以下になります。
プラスチック製品
・ペットボトル
・レジ袋
・食品容器
・プラスチック包装
劣化による細分化
ペットボトルやレジ袋などの使い捨てプラスチック製品は、適切に処理されずに環境中に放出されると、紫外線や波の力によって徐々に劣化していきます。この過程で表面が粗くなり、小さな破片が剥がれ落ちてマイクロプラスチックとなるんです。
特に海洋環境では、塩水や強い紫外線、波の力が相まって劣化が加速されます。プラスチックは自然分解されないため、一度放出されると数十年から数百年かけて徐々に小さくなっていく一方で、完全に消失することはありません。
自動車のタイヤの摩耗も重要な発生源です。走行中にタイヤから削れ落ちる微細なゴム粒子は、雨水とともに下水道を通じて海に流れ込みます。世界全体で年間約280万トンのタイヤ由来マイクロプラスチックが発生していると推計されています[2]。
身近な発生源を知ろう
私たちの日常生活で見落としがちな発生源は以下になります。
繊維製品
・ポリエステル衣類
・アクリル製品
・ナイロン素材
・フリース衣料
洗濯時の繊維脱落
合成繊維の衣類を洗濯する際に発生する繊維くずは、マイクロプラスチックの重要な発生源の一つです。一回の洗濯で、一着の合成繊維衣類から数千から数万本の微細な繊維が脱落すると報告されています。
これらの繊維くずは非常に細かいため、洗濯機の排水フィルターや下水処理場での除去が困難です。その結果、多くが海洋に流出し、海洋生物に摂取されています。
人工芝やプラスチック製の屋外用品も発生源となります。紫外線や風雨にさらされることで表面が劣化し、微細な粒子が剥がれ落ちます。食器用スポンジやメラミンスポンジなども使用により微細な破片が発生し、排水と一緒に流出する可能性があります。
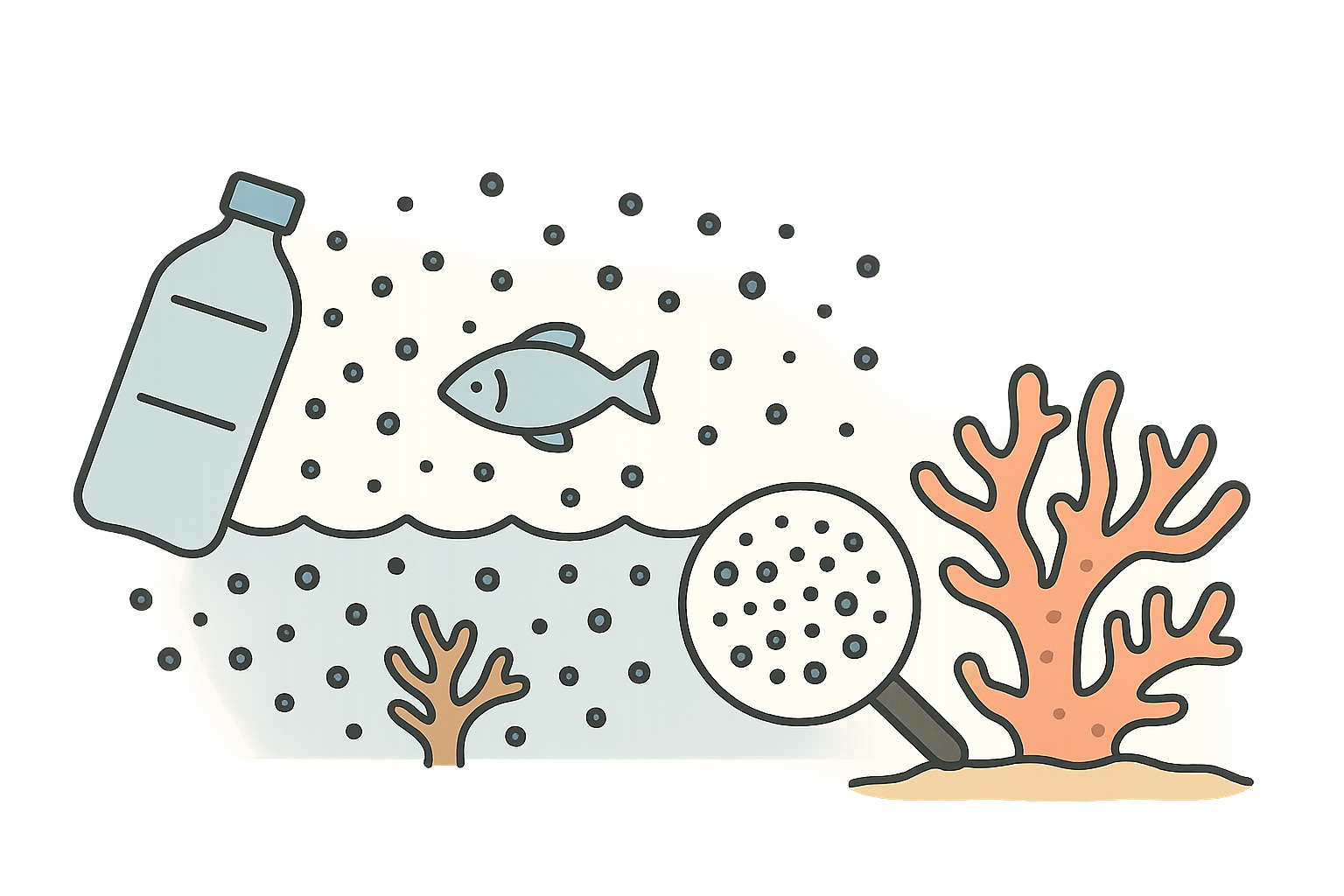
マイクロプラスチックが海洋生物に与える影響は、物理的なものと化学的なものに大別されます。
誤食による物理的被害
海洋生物がマイクロプラスチックを誤食することで起こる物理的な被害は深刻です。小さな粒子だからといって安全というわけではありません。
まず、消化器官への直接的な損傷があります。マイクロプラスチックの中には尖った形状のものもあり、これらが消化管の内壁を傷つける可能性があります。また、大量に摂取した場合、消化管が物理的に詰まってしまうこともあるんです。
さらに深刻なのは、偽の満腹感を与えることです。胃の中にプラスチックが蓄積されることで、実際の餌を食べる量が減ってしまい、栄養失調に陥る海洋生物が増加しています。クジラやウミガメの胃から大量のプラスチックごみが発見される事例が世界各地で報告されています。
繁殖能力への影響も確認されています。マガキにマイクロプラスチックを与えた実験では、卵細胞の減少や精子の運動能力低下、幼生数の減少が観察されました。これは種の存続に直結する重大な問題です[3]。
有害物質の運搬役
マイクロプラスチックの最も恐ろしい特徴の一つが、有害な化学物質を吸着・運搬する能力です。
マイクロプラスチックは、海水中に含まれる残留性有機汚染物質(POPs)を表面に吸着しやすい性質を持っています。POPsには、PCB(ポリ塩化ビフェニル)、ダイオキシン、DDTなど、人体に有害な化学物質が含まれているんです。
驚くことに、マイクロプラスチックに吸着された化学物質の濃度は、周囲の海水と比べて10万倍から100万倍にも達することがあります。つまり、マイクロプラスチックは海洋中の有害物質を高濃度に濃縮した「毒の塊」となって漂っているのです[4]。
これらの有害物質を含むマイクロプラスチックを海洋生物が摂取すると、体内で化学物質が放出され、内分泌系や免疫系に悪影響を与える可能性があります。さらに、食物連鎖を通じてより高次の捕食者に濃縮されていくため、海洋生態系全体に影響が及ぶ恐れがあるんです。
生態系のバランス破綻
マイクロプラスチック汚染は、海洋生態系の微妙なバランスを破綻させる要因となっています。
特に深刻な例として、サンゴ礁生態系への影響があります。マイクロプラスチックを多く取り込んだサンゴでは、共生している褐虫藻(かっちゅうそう)の数が減少することが確認されています。褐虫藻はサンゴと共生関係にある植物プランクトンで、光合成により作り出す有機物をサンゴに供給しているんです。
この共生関係が破綻すると、サンゴは栄養不足に陥り、白化現象や死滅につながります。サンゴ礁は「海の熱帯雨林」と呼ばれるほど生物多様性が豊かな場所であり、その破綻は海洋生態系全体に深刻な影響を与えます。
海洋生物多様性への影響も無視できません。現在までに200種類以上の海洋生物からマイクロプラスチックが検出されており、その範囲は拡大し続けています。プランクトンから大型哺乳類まで、あらゆる海洋生物が影響を受けているのが現状です[5]。
経済的な損失も深刻です。アジア太平洋地域だけでも、プラスチックごみによる年間の経済損失は、観光業で6.2億ドル、漁業・養殖業で3.6億ドルに達すると推定されています[6]。
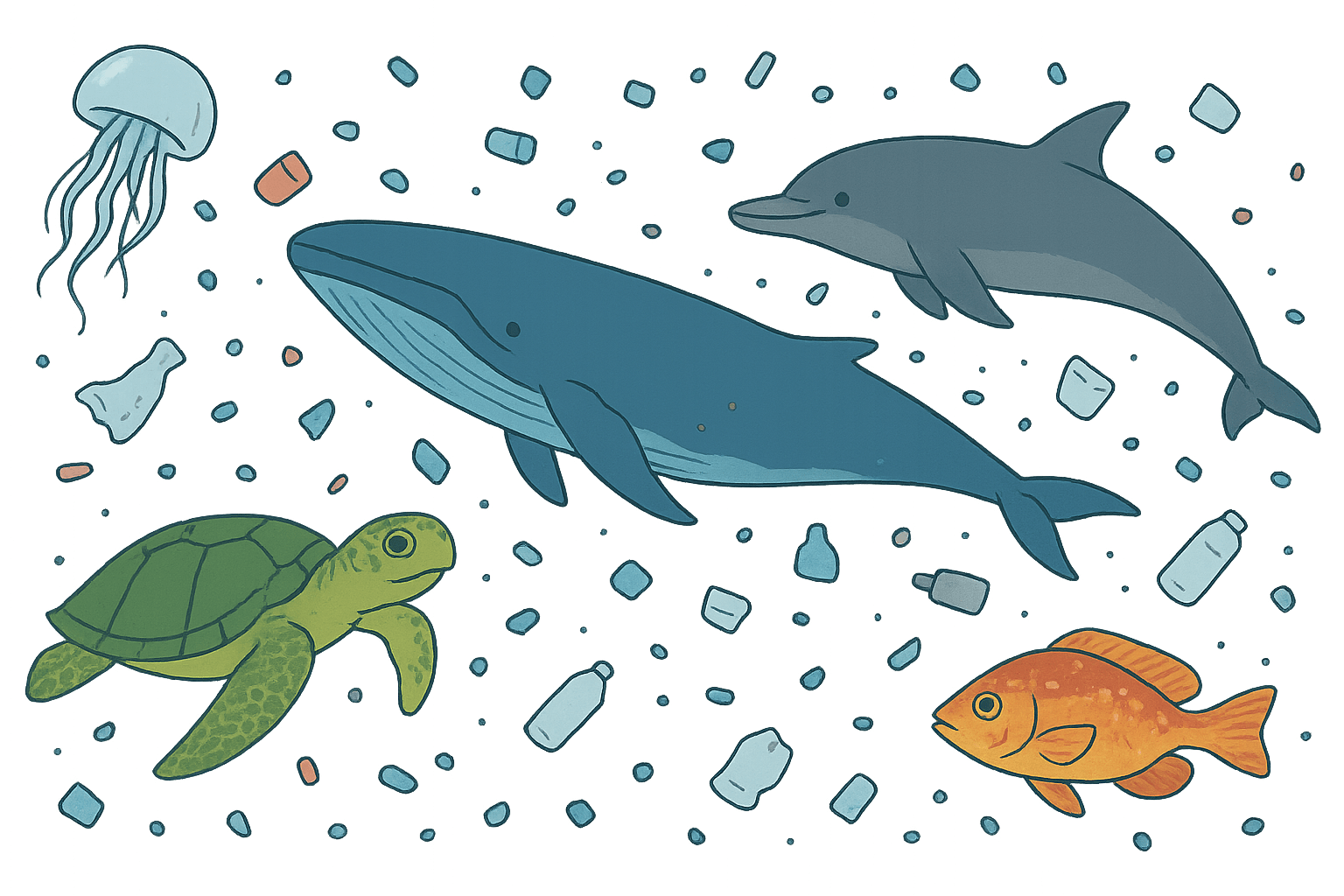
人体への影響と健康リスク
マイクロプラスチックは既に私たち人間の体内にも侵入しており、健康への影響が懸念されています。
体内への侵入経路
マイクロプラスチックが人体に侵入する経路は以下になります。
・食べ物からの摂取
・飲み物からの摂取
・空気中からの吸入
・皮膚からの吸収
多様な侵入ルート
食べ物からの摂取が最も主要な経路です。魚介類、特に二枚貝や小魚は、マイクロプラスチックを体内に蓄積しやすいことが知られています。また、海水から作られる塩にも含まれており、日常的に摂取している可能性があります。
飲み物では、ペットボトル入りの水からマイクロプラスチックが検出されています。水道水からも検出されており、完全に避けることは困難な状況です。ビールや蜂蜜からも検出されており、汚染の広がりが確認されているんですよ。
空気中からの吸入も重要な経路です。マイクロプラスチックは大気中にも漂っており、呼吸により肺に到達します。特に都市部では濃度が高く、室内外を問わず存在しています。
血液・臓器での検出報告
人体内でのマイクロプラスチック検出は、もはや特別なことではなくなっています。2022年に発表されたオランダの研究では、健康な成人22人のうち17人の血液からマイクロプラスチックが検出されました[7]。
さらに驚くべきことに、人間の様々な臓器からも検出されています。2024年の研究では、腎臓、肝臓、脳組織からマイクロプラスチックとナノプラスチックが確認されており、特に脳組織では他の臓器よりも高濃度で検出されています[8]。 検出されている臓器は多岐にわたります。心臓、肝臓、腎臓、脾臓など、主要な内臓のほとんどから検出されています。
特に衝撃的なのは、母乳や胎盤、精液からも検出されていることです。これは、次世代にも影響が及ぶ可能性を示唆しています。 最近の研究では、人間の脳組織からも検出されています。2025年にNature Medicine誌に発表されたCampenらの研究では、脳組織のマイクロプラスチック濃度が肝臓や腎臓よりも7~30倍高いことが明らかになりました[9]。
血液脳関門を通過できるほど微小なナノプラスチックが脳に到達し、神経系への影響が懸念されています。検出される粒子のサイズは主にナノスケールで、ほとんどが排出されると考えられていますが、一部は体内に蓄積している可能性があります。
健康への懸念される影響
マイクロプラスチックが人体に与える具体的な影響について、研究が進められています。
現在最も懸念されているのは、炎症反応の誘発です。人間の腸細胞を使った実験では、マイクロプラスチックが腸壁に炎症を引き起こすことが確認されています。慢性的な炎症は、様々な病気の原因となる可能性があります。
内分泌系への影響も深刻な問題です。プラスチックに含まれる添加剤の中には、環境ホルモン(内分泌攪乱物質)として知られるものがあります。例えば、フタル酸エステルという添加剤は、人の性的な成長スピードを変化させる作用があることが知られています。
免疫系への影響も報告されています。マイクロプラスチックが免疫細胞の機能を低下させ、感染症に対する抵抗力を弱める可能性が指摘されています。また、アレルギー反応を引き起こしやすくする可能性もあります。
最近の研究では、心血管疾患との関連性も示唆されています。医学誌「The New England Journal of Medicine」に掲載された研究では、血管内にたまったマイクロプラスチックと心臓発作、脳卒中、死亡リスクの高さが関連づけられました[10]。
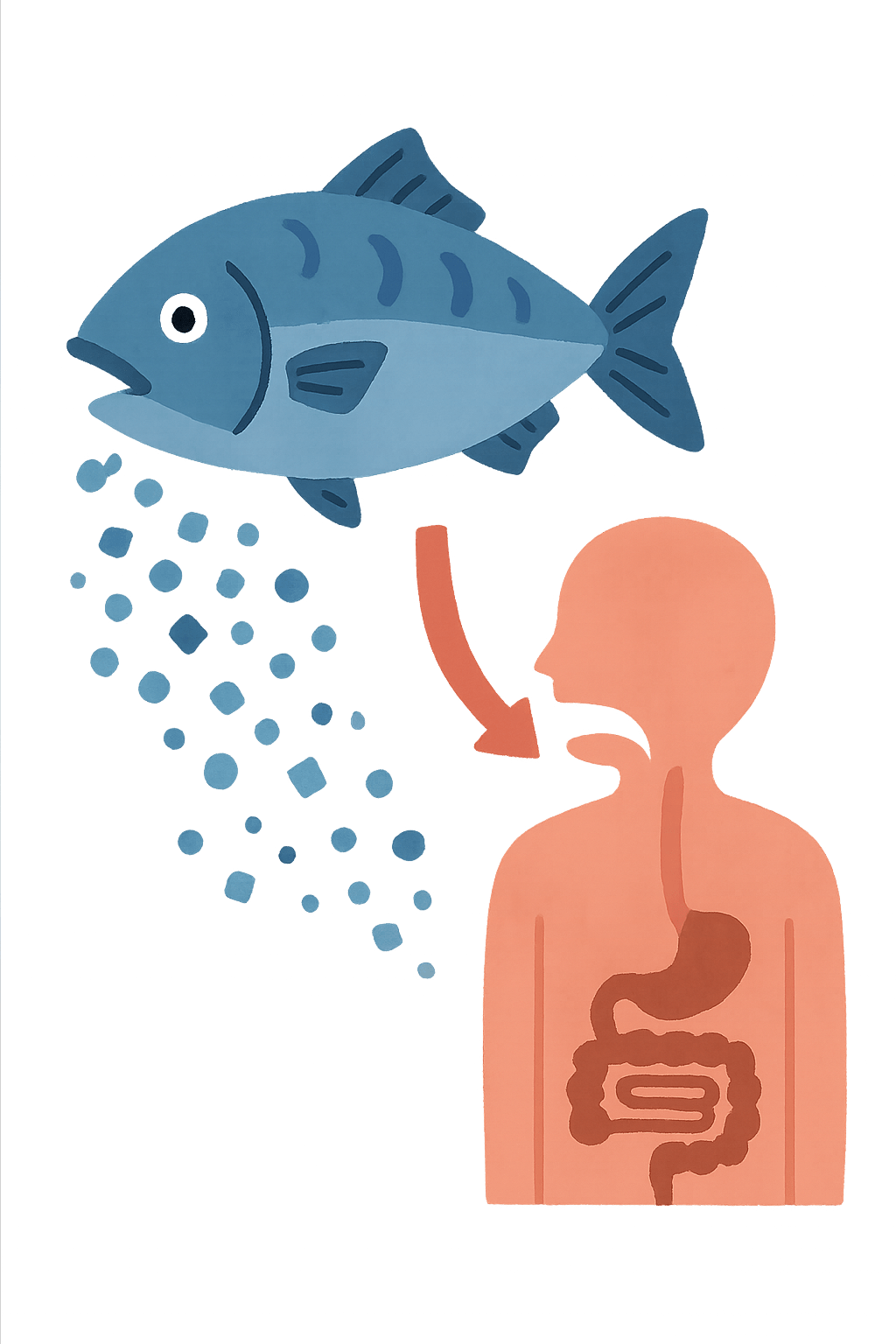
日本の深刻な汚染状況
日本周辺の海域は、世界でも特にマイクロプラスチック汚染が深刻な地域となっています。
世界の27倍の汚染レベル
2014年の環境省による海洋ごみ実態把握調査では、衝撃的な結果が明らかになりました。日本周辺海域のマイクロプラスチック濃度は、北太平洋の16倍、世界の海の平均の27倍という極めて高い数値を示したのです[11]。
この汚染レベルの高さには複数の要因があります。まず、日本は人口密度が高く、プラスチック使用量も多いことが挙げられます。使い捨てプラスチックの国民一人当たりの消費量は世界第2位となっており、大量のプラスチックごみが発生しています。
さらに、日本の地理的特徴も影響しています。島国であるため、陸上で発生したプラスチックごみが河川を通じて比較的短時間で海に到達しやすい環境にあります。また、沿岸部に人口や産業が集中していることも、海洋汚染を加速させる要因となっています。
包装文化も一因です。日本では商品の過剰包装が一般的で、個包装や二重包装などが日常的に行われています。これにより、他国と比較して使い捨てプラスチックの使用量が格段に多くなっています。
東京湾の調査結果
東京湾で行われた調査では、マイクロプラスチック汚染の実態がより具体的に明らかになりました。
東京湾で捕獲されたカタクチイワシの調査では、64匹中49匹からマイクロプラスチックが検出されました。検出率は約8割に達し、合計で150個のマイクロプラスチックが発見されています。
特に注目すべきは、検出されたマイクロプラスチックの約1割が洗顔料などの生活用品に使用されているマイクロビーズだったことです。これは、私たちの日常生活が直接的に海洋汚染につながっていることを示す明確な証拠です。
東京湾は閉鎖性の高い海域であるため、一度流入したマイクロプラスチックが長期間滞留しやすい特徴があります。このため、汚染の蓄積が進みやすく、生態系への影響も深刻化しています。
黒潮による流入問題
日本周辺海域のマイクロプラスチック汚染には、黒潮による他国からの流入も影響しています。
黒潮は、フィリピン沖から日本列島に沿って北上する強い海流です。この海流により、東南アジア諸国から発生したプラスチックごみが日本周辺海域に運ばれてきます。特に中国や東南アジア諸国では、廃棄物管理システムが十分に整備されていない地域があり、大量のプラスチックごみが海洋に流出しています。
神奈川県の調査では、相模湾に漂着するマイクロプラスチックの由来が、外洋からではなく内陸部から河川を通じて流出している可能性が高いことが判明しています。これは、国内での発生源対策の重要性を示しています。
しかし、海流による広域移動も無視できません。マイクロプラスチックは海流に乗って数千キロメートルも移動するため、一国だけの努力では解決できない国際的な問題となっています。このため、アジア太平洋地域全体での協力体制が不可欠です。
個人・企業・社会ができること
マイクロプラスチック問題の解決には、個人、企業、国際社会それぞれのレベルでの取り組みが必要です。
個人でできる取り組み
私たち一人ひとりができる対策は以下になります。
・マイバッグの持参
・マイボトルの使用
・プラスチック容器の削減
・適切な分別処理
身近な行動から変化
最も効果的で簡単な対策は、使い捨てプラスチックの使用を減らすことです。買い物の際にマイバッグを持参してレジ袋をもらわない、マイボトルを使ってペットボトルの購入を控えるなど、日常的な習慣を変えることで大きな効果が期待できます。
商品選択も重要です。過剰包装された商品を避け、プラスチック包装の少ない商品を選ぶことで、需要側からプラスチック使用量の削減を促すことができます。また、マイクロビーズを含まない洗顔料や歯磨き粉を選ぶことも効果的です。
衣類選択では、天然繊維(綿、麻、羊毛など)の衣類を選ぶことで、洗濯時の繊維くず発生を抑制できます。合成繊維の衣類を洗濯する際は、低温で短時間の設定にすることで繊維の脱落を減らすことができます。
ごみの適切な処理も重要です。分別ルールを守り、リサイクル可能なものは確実にリサイクルに回すことで、環境への流出を防げます。また、屋外でのごみのポイ捨ては絶対に避け、ごみ拾い活動に参加することも有効です。
企業の革新的取り組み
企業レベルでの取り組みは以下になります。
・生分解性素材の開発
・マイクロビーズ代替技術
・回収・除去システム
・代替包装材の導入
革新技術による解決
生分解性プラスチックの開発は、根本的な解決策として期待されています。海水中でも分解される素材の開発が進んでおり、カネカの「Green Planet」シリーズや三菱ケミカルの海洋生分解性プラスチックなど、実用化が始まっています。
マイクロビーズの代替技術も進歩しています。AGCが開発した天然由来シリカビーズ、レンゴーのセルロース系代替材料など、天然素材を活用した代替品が実用化されています。これらは従来のマイクロビーズと同等の機能を持ちながら、環境負荷が大幅に軽減されています。
回収・除去技術の開発も重要です。島津製作所の自動前処理装置、JFEエンジニアリングのバラスト水処理装置など、環境中のマイクロプラスチックを効率的に回収する技術が実用化されています。また、スズキの船外機用回収装置など、移動しながら回収を行う技術も開発されています。
繊維業界では、洗濯時の繊維くず抑制技術が注目されています。帝人フロンティアの機能性テキスタイル、タキヒヨーのLMP認証繊維など、繊維脱落を大幅に抑制する素材の開発が進んでいます。
国際的な規制強化
世界レベルでの取り組みは以下になります。
国際的な枠組み
・大阪ブルー・オーシャン・ビジョン
・プラスチック汚染条約
・各国の法規制
・国際協力体制
グローバルな対策
2019年のG20大阪サミットで提唱された「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」は、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにすることを目指しています。現在87の国・地域がこのビジョンを共有しており、国際的な取り組みの基盤となっています[12]。
国連では、プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際条約の策定が進められています。2022年から政府間交渉委員会での議論が開始され、マイクロプラスチックを含むプラスチック汚染の包括的な対策が検討されています。
各国でも規制強化が進んでいます。欧州連合(EU)では使い捨てプラスチック製品の規制、アメリカではマイクロビーズ禁止法の制定、カナダでは使い捨てプラスチック6品目の製造・販売禁止など、具体的な規制措置が取られています。
日本でも2019年に海岸漂着物処理推進法が改正され、事業者に対してマイクロプラスチックの使用抑制努力義務が課されました。また、2022年4月からプラスチック資源循環促進法が施行され、プラスチック使用製品の設計から廃棄まで、ライフサイクル全体での対策が求められています。
まとめ
マイクロプラスチック問題は、私たちの日常生活と密接に関わる深刻な環境・健康問題です。目に見えないほど小さな粒子でありながら、海洋生態系から人体まで広範囲にわたって影響を与えています。
日本周辺海域の汚染レベルは世界平均の27倍と極めて深刻で、私たちの血液や内臓からも検出されているのが現実です。しかし、この問題は決して絶望的なものではありません。一人ひとりの行動変化、企業の技術革新、国際的な協力により、解決への道筋は見えています。
今日からできることは沢山あります。マイバッグを持参する、マイボトルを使う、過剰包装を避ける、適切にごみを分別するなど、小さな行動の積み重ねが大きな変化を生み出します。未来の地球と私たちの健康のために、今すぐ行動を起こしませんか?4
お知らせ
最後まで、読んでいただき光栄です。私たち都市環境サービスは、プラスチックリサイクルに特化した会社です。フラフ燃料の製造や代替燃料に興味がある方、リサイクルの会社で働いてみたい方は、こちらのフォームから気軽にお問合せください。よろしくお願いします。



