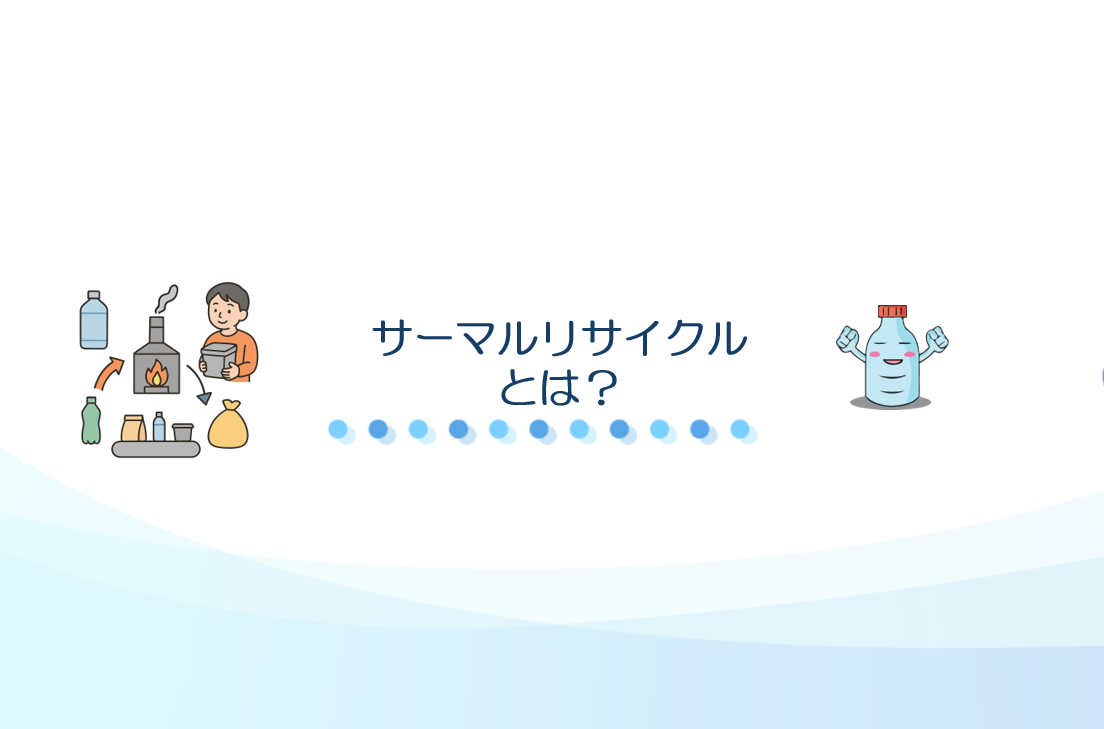皆さんこんにちは。今回のテーマは「サーマルリサイクル」です。ごみを燃やして出る熱を電気や温水に変える仕組み、聞いたことはありませんか?

実はこのサーマルリサイクル、日本では廃プラスチックの処理方法として約6割を占めているんです[1]。でも世界からは「それって本当にリサイクル?」という声も上がっているんですよ。本記事では、サーマルリサイクルの仕組みからメリット・問題点、そして日本で広く普及している理由まで詳しく解説していきます。
目次は以下の通りです。
① サーマルリサイクルとは
② 日本に多い3つの理由
③ どこで使われている?
④ 5つのメリット
⑤ 3つの問題点
⑥ 世界との認識の違い
⑦ これからの方向性
サーマルリサイクルは環境問題を考える上で欠かせないテーマです。ぜひ最後までご一読ください。
サーマルリサイクルとは
サーマルリサイクルは、ごみを燃やしたときに出る熱を回収して利用する処理方法です。ここでは基本的な仕組みから他のリサイクルとの違いまで見ていきましょう。
ごみを燃やして熱を回収
サーマルリサイクルとは、廃棄物を焼却する際に発生する熱エネルギーを回収して利用する方法のことです。「サーマル」は英語で「熱」を意味し、「熱回収」や「エネルギー回収」とも呼ばれています。
主に廃プラスチック類が対象になります。プラスチックは石油から作られているため、石炭や石油と同じくらい高いエネルギー量を持っているんですよ。そのため燃やすと大量の熱が発生し、この熱を無駄にせず発電や暖房などに活用するわけです。
具体的には、ごみ焼却施設で廃棄物を燃やし、その際に発生する熱で水を沸騰させて蒸気を作ります。この蒸気でタービンを回して発電したり、温水として施設の暖房や給湯に使ったりします。
他のリサイクルとの違い
リサイクルには大きく分けて3つの種類があります。それぞれの特徴は以下になります。
リサイクルの種類
マテリアルリサイクル
ケミカルリサイクル
サーマルリサイクル
マテリアルリサイクルは、廃棄物をそのまま原料として再利用する方法です。ペットボトルを粉砕して繊維にし、衣類の原料にするのが代表例ですね。
ケミカルリサイクルは、廃棄物を化学的に分解して原料レベルまで戻してから、新しい製品を作る方法です。ペットボトルからペットボトルを作ることができます。
一方、サーマルリサイクルは物質そのものを再利用するのではなく、燃やして得られるエネルギーを利用する点が大きく異なります。そのため海外では「リサイクルではない」と指摘されることもあるんです。
処理の流れと仕組み
サーマルリサイクルの基本的な処理の流れは以下になります。
処理の流れ
ごみの収集
廃棄物の分別
焼却炉で燃焼
熱の回収と利用
まず家庭や事業所から出たごみを回収し、焼却施設に運びます。施設では燃えるごみと燃えないごみを分別し、サーマルリサイクルに適した廃棄物を選別します。
次に焼却炉で廃棄物を高温で燃やします。この時、完全燃焼させることで有害物質の発生を抑えながら、効率よく熱エネルギーを取り出すことができます。
発生した熱は蒸気ボイラーで回収され、発電用のタービンを回したり、温水として近隣施設に供給されたりします。排ガスは処理装置で有害物質を取り除いてから大気に放出されます。
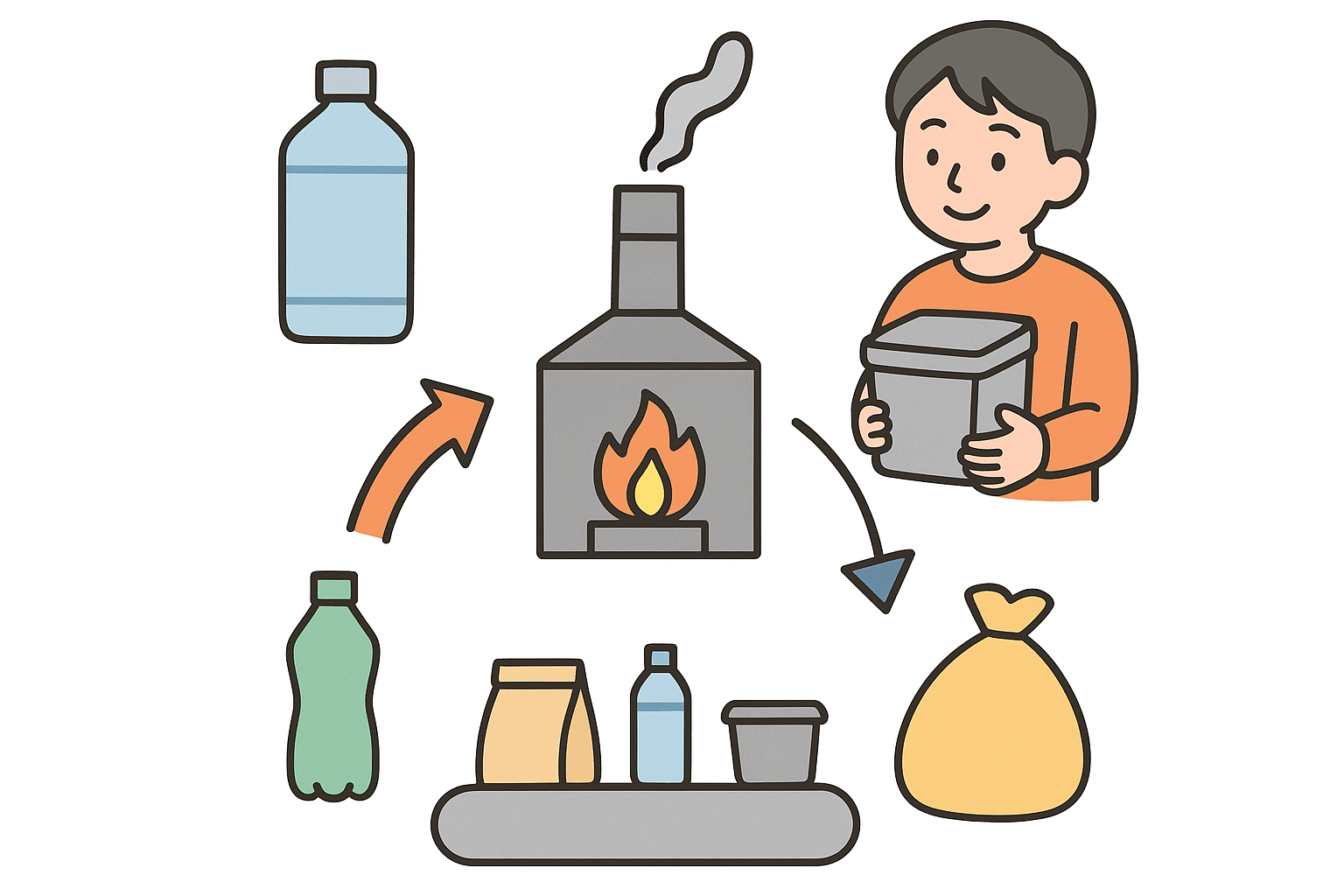
日本に多い3つの理由
日本では廃プラスチックの約62%がサーマルリサイクルで処理されています[1]。なぜこれほど多いのか、その背景を見ていきましょう。
輸出規制の影響
日本でサーマルリサイクルが増えた大きな理由の一つが、廃プラスチックの輸出規制です。以前は中国や東南アジアに廃プラスチックを資源として輸出していました。
しかし2019年、バーゼル条約の改正により汚れた廃プラスチックの輸出が規制対象になりました。これにより輸出量が大幅に減少し、国内で処理する必要性が高まったんです。
輸出できなくなった廃プラスチックをどう処理するか。マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルには設備や分別の手間がかかります。そこで比較的導入しやすいサーマルリサイクルが選ばれるようになりました。
埋立地の不足
日本は国土が狭く、ごみの最終処分場である埋立地が限られています。新しい埋立地を作るのも場所の確保が難しく、既存の処分場を長く使う必要があるんですよ。
リサイクルできないごみは埋め立て処分されますが、埋立地には容量の限界があります。サーマルリサイクルを行うことで、ごみの体積を約30分の1に減らすことができるため、埋立地の延命につながります。
特にプラスチックは埋め立てても自然分解されず、そのまま残り続けます。さらに劣化すると温室効果ガスであるメタンガスを発生させてしまうため、焼却して熱エネルギーとして回収する方が環境負荷を減らせると考えられています。
技術力の高さ
日本は世界的に見てもごみ焼却技術が優れています。全国に約1,000か所以上のごみ焼却施設があり、そのうち約70%が何らかの形で余熱を利用しているんです。
高温での完全燃焼技術や排ガス処理技術が発達しており、有害物質の排出を抑えながら効率的にエネルギーを回収できます。この技術的な土台があったからこそ、サーマルリサイクルが普及しやすかったと言えます。
また既存の焼却施設を活用できるため、新たに大規模な設備を建設する必要が少ないのも導入しやすい理由です。コストを抑えながら廃プラスチックの処理ができる点が評価されています。
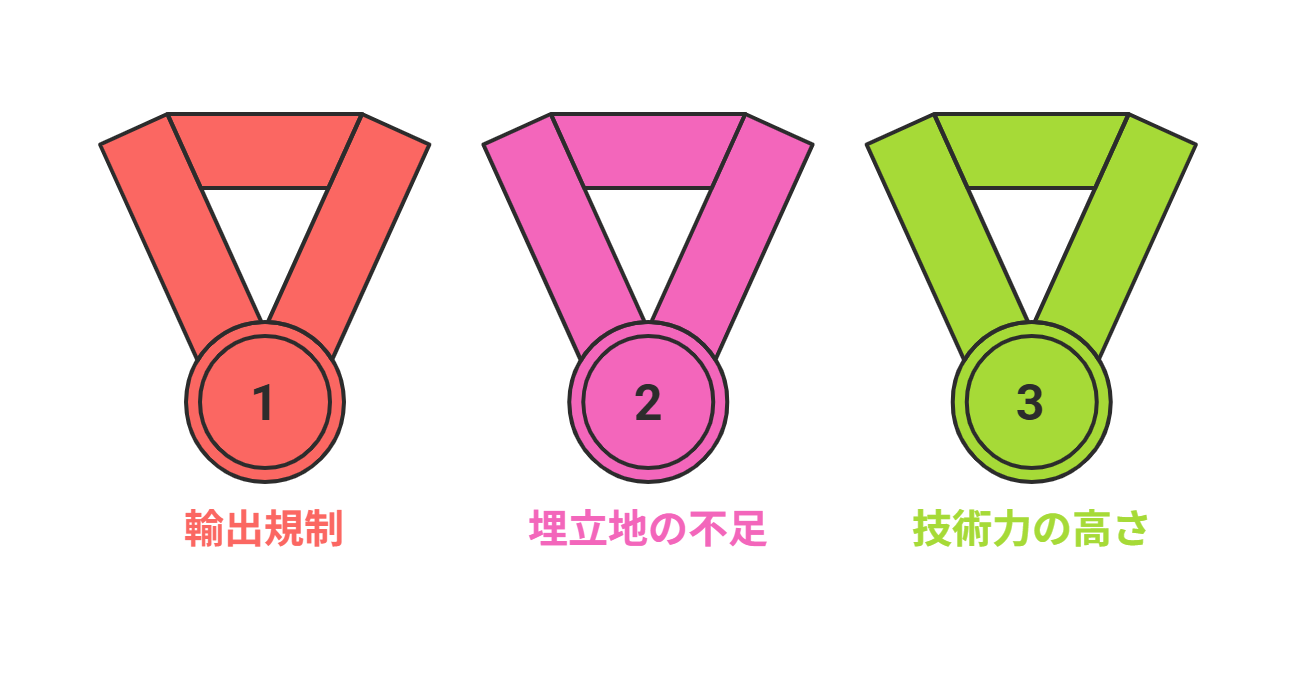
どこで使われている?
サーマルリサイクルで回収された熱エネルギーは、私たちの身近なところで活用されています。具体的な利用例を見ていきましょう。
ごみ発電
最も多い利用方法がごみ発電です。全国の一般廃棄物焼却施設のうち、約34%に発電設備が設置されています。年間の総発電電力量は約10,452ギガワット時にもなり、これは約250万世帯の年間電力消費量に相当します。
ごみ焼却施設では、廃棄物を燃やした熱で水を蒸気に変えます。その高温高圧の蒸気でタービンを回して発電する仕組みです。発電した電気は施設内で使うだけでなく、余った分は電力会社に売却されることもあります。
例えば大阪広域環境施設組合では、令和3年度に約15万世帯が1年間で使用する電力量を発電しました。ごみを処理しながら電力を生み出せるのは、資源の有効活用として大きな意味があります。
温水プール
ごみ焼却施設の隣に温水プールを設置している自治体も多くあります。焼却時の熱で温めた温水をプールに供給することで、一年中温水プールを利用できるようにしているんですよ。
仙台市の葛岡温水プールはその代表例です。隣接するごみ焼却工場の余熱を利用して、冬でも快適に泳げる温水プールを運営しています。燃料費をかけずに温水を作れるため、施設の運営コストも抑えられます。
温水プール以外にも、浴場施設や健康増進施設に温水を供給している例もあります。地域住民が気軽に利用できる施設として親しまれており、サーマルリサイクルの恩恵を実感できる場所になっています。
工場の暖房
ごみ焼却施設や近隣の工場の暖房・給湯にも活用されています。焼却時に発生した熱で作った蒸気を、配管を通じて施設内や周辺の建物に送る仕組みです。
大阪広域環境施設組合の例では、ボイラーで得た蒸気を工場内の暖房や給湯に使用しています。さらに近隣施設にも蒸気を提供したり、電気事業者へ売却したりと、熱エネルギーを余すことなく活用しています。
冬場の暖房需要が高い時期には特に効果的で、化石燃料を燃やして暖房する必要がなくなります。環境負荷を減らしながらエネルギーコストも削減できる一石二鳥の方法です。
ビニールハウス
農業分野でもサーマルリサイクルが活用されています。新潟県柏崎市の産業廃棄物処理業者では、廃棄物処理時の排熱をビニールハウスの温度管理に利用しています。
この取り組みで栽培されているのが「越後バナーナ」という国産バナナです。雪国でありながら熱帯果物の栽培を実現し、地域の特産品として注目を集めています。
ビニールハウスの温度管理には通常、重油などの燃料を使って暖房します。しかしサーマルリサイクルの熱を使えば燃料費がかからず、環境にも優しい農業ができます。地域資源の循環という点でも意義深い取り組みです。
5つのメリット
サーマルリサイクルには環境面・経済面でさまざまなメリットがあります。主な利点を5つ紹介していきます。
汚れたごみも処理可能
サーマルリサイクル最大のメリットは、汚れや異物が付いた廃棄物でも処理できることです。マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルでは、きれいに分別された状態の廃棄物が必要になります。
例えば宅配ピザの箱は油や食べかすが付着しているため、古紙としてリサイクルできません。また複数の素材を組み合わせたラミネートフィルムなども、材質ごとに分けるのが困難です。
しかしサーマルリサイクルなら高温で燃やすため、汚れや異物があっても問題なく処理できます。分別の手間が省け、リサイクルが難しかったごみも有効活用できるんですよ。
石油の節約
廃プラスチックは石油から作られているため、燃やすと石油や石炭と同等の熱エネルギーが得られます。紙ごみの2〜3倍もの発熱量があり、非常に効率的な燃料になるんです。
サーマルリサイクルで発電や暖房をすることで、本来使うはずだった化石燃料の消費を減らせます。火力発電所で燃やす石油の量を間接的に削減できるため、限りある資源の節約につながります。
また化石燃料を輸入に頼る日本にとって、国内の廃棄物をエネルギー源として活用できることは、エネルギー自給率の向上という面でもメリットがあります。
埋立地の延命
サーマルリサイクルを行うことで、ごみの体積を大幅に減らすことができます。焼却によって廃棄物の体積は約30分の1になり、埋立処分が必要な量が激減します。
日本の最終処分場は限られており、新たに作るのも困難な状況です。既存の埋立地をできるだけ長く使うためには、埋め立てるごみの量を減らす必要があります。
サーマルリサイクルによって埋立地の寿命を延ばせることは、将来世代のためにも重要です。処分場不足という深刻な問題の解決策の一つとして機能しています。
メタンガス削減
プラスチックごみを埋め立てると、劣化する過程でメタンガスが発生します。メタンガスは二酸化炭素の約25倍もの温室効果があり、地球温暖化の大きな原因になるんですよ。
サーマルリサイクルでプラスチックを焼却すれば、メタンガスの発生を防ぐことができます。焼却時に二酸化炭素は出ますが、メタンガスと比べれば温室効果は小さいため、環境負荷の低減につながります。
特に食品が付着したプラスチック類は、埋め立てると食品の腐敗によってさらに多くのメタンガスが発生します。焼却処理することで、こうした問題を回避できます。
低コスト
サーマルリサイクルは比較的低コストで実施できます。既存のごみ焼却施設に熱回収設備を追加すればよく、ゼロから大規模な施設を建設する必要がありません。
ケミカルリサイクルには専用の化学工場が必要で、設備投資に莫大な費用がかかります。マテリアルリサイクルも分別や洗浄の手間がかかり、コストが高くなりがちです。
その点サーマルリサイクルは処理が容易で、分別にかける労力も少なくて済みます。全国に焼却施設のインフラがすでにあることも、導入コストを抑えられる理由になっています。
3つの問題点
メリットがある一方で、サーマルリサイクルにはいくつかの問題点も指摘されています。主な課題を3つ見ていきましょう。
二酸化炭素の排出
サーマルリサイクル最大の問題点は、焼却時に二酸化炭素が排出されることです。日本では廃プラスチックの焼却により、年間約1,600万トンもの二酸化炭素が排出されています[2]。
プラスチックは化石燃料から作られているため、燃やすと必ず二酸化炭素が発生します。地球温暖化対策が世界的な課題となる中、この二酸化炭素排出が大きな懸念材料になっています。
2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする目標に向けて、サーマルリサイクルだけに頼り続けることは難しくなっています。より環境負荷の低いリサイクル方法への転換が求められているんです。
有害物質の発生
ごみを焼却すると、ダイオキシンなどの有害物質が発生する可能性があります。ダイオキシンは発がん性があり、人体に深刻な影響を及ぼす危険な物質です。
近年は燃焼技術の進化や規制の強化により、有害物質の排出量は大幅に減少しています。高温での完全燃焼や排ガス処理装置の性能向上によって、かなり安全に処理できるようになりました。
しかし完全にゼロにすることは難しく、微量ながら有害物質は発生し続けています。また焼却後の灰には鉛や水銀などの重金属が残ることもあり、適切な処理が必要です。
設備コスト
サーマルリサイクルを実施するには、それなりの設備投資が必要です。焼却炉、蒸気ボイラー、発電用タービン、排ガス処理装置など、多くの設備を整えなければなりません。
特に高効率な発電を行うためには最新の技術を導入する必要があり、コストがかさみます。古い焼却施設を改修する場合も、大規模な工事が必要になることがあります。
また施設によって性能に差があり、地域によって処理能力や発電効率が異なります。全国一律の基準で運用するのが難しく、効率的な熱回収ができていない施設も存在しているのが現状です。

世界との認識の違い
日本ではリサイクルの一つとされるサーマルリサイクルですが、世界的には異なる見方があります。その違いを理解しておきましょう。
欧米の考え方
欧米をはじめとする多くの国では、サーマルリサイクルを「リサイクル」とは認めていません。英語では「エネルギー回収(Energy Recovery)」や「熱回収(Thermal Recovery)」と呼ばれています。
欧米でリサイクルといえば、廃棄物を新しい製品の原料として再利用することを指します。物質そのものが循環する仕組みこそが真のリサイクルという考え方なんですよ。
一方サーマルリサイクルは廃棄物を燃やしてしまうため、物質としては消滅します。エネルギーは回収できますが、再び製品の原料にはなりません。この点が「リサイクルではない」とされる理由です。
日本の現状
日本はプラスチックのリサイクル率を約87%としていますが、そのうち約62%がサーマルリサイクルです[1]。つまりリサイクル率の大部分を、サーマルリサイクルが占めているわけです。
容器包装リサイクル法などの日本の法律では、サーマルリサイクルも正式なリサイクル方法の一つとして位置づけられています。循環型社会形成推進基本法でも、熱回収は廃棄物処理の選択肢として認められています。
ただし日本国内でも最近は「サーマルリカバリー」という表現を使う企業が増えています。国際的な認識に合わせて、リサイクルとは区別する動きも出てきているんです。
本当のリサイクル率
欧米基準でサーマルリサイクルを除外すると、日本の真のリサイクル率は約19%程度になります。OECDの調査によると、これは加盟34か国中27位という低い水準です。
一見高く見える日本のリサイクル率は、サーマルリサイクルを含めた数字なんですよ。マテリアルリサイクルとケミカルリサイクルだけで見ると、実は世界的に見て低いレベルにあります。
欧米諸国ではマテリアルリサイクルを中心に据えた政策を進めており、日本とは大きく異なるアプローチを取っています。今後国際的な評価を得るためには、日本もリサイクルの質を高めていく必要があります。
これからの方向性
サーマルリサイクルの位置づけを踏まえ、今後どのような方向性が求められるのか考えていきましょう。
優先順位の考え方
循環型社会形成推進基本法では、廃棄物処理の優先順位が定められています。その順位は以下になります。
処理の優先順位
発生抑制
再使用
再生利用
熱回収
適正処分
最も優先すべきは、そもそもごみを出さないこと(発生抑制)です。次に使えるものは繰り返し使うこと(再使用)、そして材料として再生すること(再生利用)が来ます。
サーマルリサイクル(熱回収)は4番目の選択肢なんです。つまり他の方法が難しい場合の最終手段として位置づけられています。まずはごみを減らし、リユースやマテリアルリサイクルを優先することが重要です。
2022年施行のプラスチック資源循環促進法でも、使い捨てプラスチックの削減が求められています。サーマルリサイクルに頼り過ぎない社会づくりが進められているんですよ。
技術開発の必要性
サーマルリサイクルの課題を解決するには、技術開発が欠かせません。特に発電効率の向上と二酸化炭素排出の削減が重要なテーマです。
現在、発電効率が20%以上の施設は全国でわずか37か所しかありません。多くの焼却施設では熱を十分に活用できていないのが実態です。新しい焼却技術の導入により、効率を高める取り組みが必要です。
また将来的には、排出される二酸化炭素を回収して再利用する「カーボンリサイクル」技術の開発も期待されています。サーマルリサイクルをより環境に優しい方法に進化させていくことが求められています。
まとめ
サーマルリサイクルは、ごみを燃やして熱エネルギーを回収する処理方法です。日本では廃プラスチックの約6割がこの方法で処理されており、発電や温水利用など私たちの生活を支えています。
輸出規制や埋立地不足といった日本特有の事情により普及しましたが、二酸化炭素の排出や世界との認識の違いなど、課題も抱えています。
今後は発生抑制や再使用を優先しつつ、サーマルリサイクルもより効率的で環境に優しい技術へと進化させていく必要があります。私たち一人ひとりができることは、まずごみを減らすこと。そしてリサイクルに適したごみの分別を正しく行うことです。環境のために、今日から身近なところから始めてみませんか?