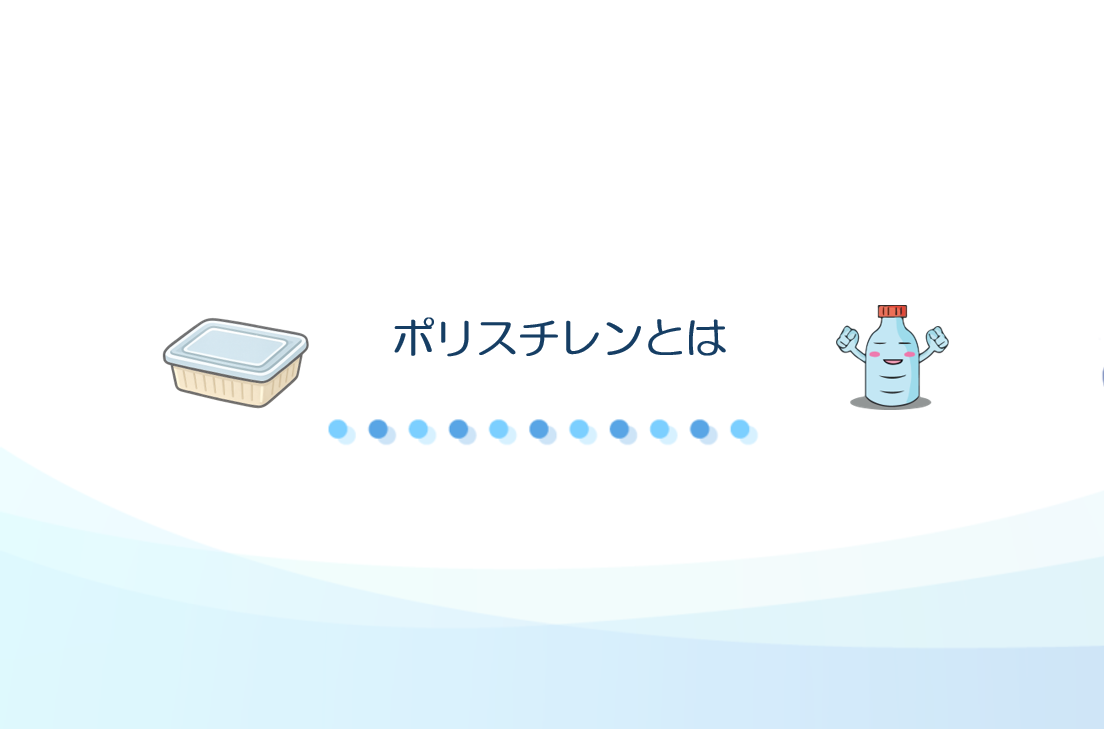皆さんこんにちは。都市環境サービスの前田です。今回のテーマは「ポリスチレンとは」です。スーパーでの食品トレイやテレビのケース、発泡スチロールなど、実は私たちの身の回りにはポリスチレンで作られた製品があふれているんです。

実は、ポリスチレンは5大汎用樹脂の一つとして、私たちの生活を支える重要な素材なんですよ。環境問題が注目される今、このプラスチックについて正しく理解することで、適切な分別やリサイクルにつなげることができます。本記事では、ポリスチレンの基本的な特徴から製造方法、用途、環境への配慮まで詳しく解説していきます。
目次は以下の通りです。
①ポリスチレンとは
②ポリスチレンの歴史
③ポリスチレンの製造方法
④ポリスチレンの種類
⑤ポリスチレンの特徴
⑥ポリスチレンの長所
⑦ポリスチレンの短所
⑧日常生活での用途
⑨産業分野での用途
⑩発泡スチロールの特徴
⑪5大汎用樹脂の位置づけ
⑫安全性と食品への利用
⑬環境への配慮
⑭ポリスチレンの識別方法
ポリスチレンは環境にも配慮された循環型社会の実現に貢献する素材なんです。ぜひ最後までご一読ください。
ポリスチレンとは
まず、ポリスチレンの基本的な概念と特性について詳しく見ていきましょう。
基本的な定義と特徴
ポリスチレンとは、石油を原料として作られるプラスチックの一種です。英語では「polystyrene」と書かれ、略して「PS」と表記されることが多いんですよ。このプラスチックは、スチレンという化学物質を原料として、たくさんの分子をつなげて作られています。
ポリスチレンの最大の特徴は、透明で硬く、軽量であることです。また、電気を通さない性質があるため、電気製品の部品としても重宝されています。世界中で約1000万トンものポリスチレンが使用されており、私たちの生活に欠かせない素材となっています[1]。
化学式と分子構造
ポリスチレンの化学式は「(C8H8)n」で表されます。これは、炭素8個と水素8個からなる「スチレン」という分子が、n回繰り返しつながっていることを意味しています。この「n」は重合度と呼ばれ、通常数百から数千の値になります。
分子の構造を簡単に説明すると、背骨のような主鎖に、ベンゼン環という六角形の構造がぶら下がっている形になっています。このベンゼン環が、ポリスチレンに透明性や硬さを与える重要な役割を果たしているんです。
PSという略号について
製品の表示や業界では、ポリスチレンを「PS」という略号で表すことが一般的です。これは「Poly Styrene」の頭文字を取ったものです。プラスチック製品の底面を見ると、三角形のリサイクルマークの中に「6」という数字と、その下に「PS」と書かれていることがあります。
この「6」という数字は、樹脂識別コード(SPIコード)と呼ばれるもので、プラスチックの種類を区別するための国際的な表示方法です。スーパーで買い物をする際に、容器の底を確認してみると、様々な数字とアルファベットが見つかりますよ。

ポリスチレンの歴史
ポリスチレンがどのように発見され、発展してきたのかを時系列で見ていきましょう。
発見と初期の研究
ポリスチレンの発見は、1839年にまで遡ります。ドイツの化学者エドワード・シモンが、天然の樹脂から固形物として初めて発見しました。しかし、この時点ではまだその正体や性質について詳しく分かっていませんでした。
その後、1920年代になってからドイツのシュタウディンガーらによって、スチレンという小さな分子が鎖状につながった高分子物質であることが分かりました。高分子とは、たくさんの分子が手をつないで長い鎖のようになった物質のことです。この発見により、ポリスチレンの本格的な研究が始まったんです。
工業化の始まり
ポリスチレンが実際に工業製品として製造されるようになったのは、1930年代のことです。1935年にドイツで初めて工業化され、その後1937年頃にはアメリカでも生産が始まりました。これにより、ポリスチレンは実験室の中だけでなく、実際の製品として使われるようになりました。
第二次世界大戦中には、金属が軍事用に使われるため不足し、その代替品としてプラスチックの需要が急激に高まりました。ポリスチレンも、この時期に大きく発展することになったのです。戦後になると、安価で便利なプラスチックとして民間でも広く使われるようになりました。
日本での普及経緯
日本では、第二次世界大戦中にポリスチレンの研究が行われましたが、実用化には至りませんでした。戦後の1940年代後半になって、海外からの輸入が始まり、1950年代後半には海外からの技術導入により、ようやく国内での工業化に成功しました。
その後、日本独自の技術開発も進み、製造メーカーが増加していきました。1950年に発泡スチロールの製造も開始され、1959年からは本格的な生産が始まりました。現在では、DIC、東洋スチレン、PSジャパンの3社が国内の主要なポリスチレン製造メーカーとなっています。

ポリスチレンの製造方法
ポリスチレンがどのような工程を経て作られるのかを、分かりやすく説明していきます。
原料となるナフサ
ポリスチレンの製造は、石油から始まります。石油を精製する過程で得られる「ナフサ」という油が、ポリスチレンの原料となります。ナフサは、ガソリンよりも軽い成分で、様々な化学製品の原料として使われている重要な物質なんです。
このナフサを高温で分解することによって、エチレンやベンゼンといった基本的な化学物質を取り出します。これらの物質が、最終的にポリスチレンの材料となるスチレンモノマーを作るための原料となるのです。石油から様々な化学製品が作られることを石油化学工業と呼んでいます。
スチレンモノマーの生成
ナフサから取り出したベンゼンとエチレンを化学反応させると、エチルベンゼンという物質ができるんです。このエチルベンゼンをさらに高温で加熱することによって、スチレンモノマーが生成されます。モノマーとは、ポリマー(高分子)を作るための最小単位の分子のことです。
スチレンモノマーは、無色透明の液体で、独特の香りがします。この段階では、まだプラスチックではありません。スチレンモノマーは不安定な物質で、時間が経つと自然に重合してしまうため、製造から使用までの管理が重要になるんですよ。
重合プロセスの仕組み
スチレンモノマーからポリスチレンを作る工程を重合と呼びます。重合とは、小さな分子(モノマー)がたくさんつながって、大きな分子(ポリマー)になることです。これは、小さなブロックをつなげて大きな建物を作るようなイメージです。
工業的には、ラジカル重合という方法が主に使われています。これは、特殊な薬品(開始剤)を加えて化学反応を起こし、スチレンモノマー同士を次々とつなげていく方法です。反応の条件を調整することで、分子の大きさや性質を変えることができ、用途に応じた様々なポリスチレンを作ることができるんです。
ポリスチレンの種類
ポリスチレンには、用途に応じて様々な種類があります。主要なタイプを見ていきましょう。
汎用ポリスチレン(GPPS)
汎用ポリスチレン(GPPS)は、「General Purpose Polystyrene」の略で、最も基本的なポリスチレンです。透明で硬く、光をよく通すという特徴があります。プラスチックの中でも特に透明度が高く、ガラスのような美しい透明感を持っています。
GPPSは、CDケースやプラスチックの定規、透明な容器などに広く使われています。加工がしやすく、精密な形状を作ることができるため、細かい部品の製造にも適しています。ただし、衝撃に弱いという欠点があり、強い力が加わると割れてしまうことがあるんです。
耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)は、「High Impact Polystyrene」の略で、GPPSにゴム成分を加えて衝撃に強くしたポリスチレンです。ゴムを加えることで、割れにくく、丈夫になりました。その代わり、透明度は失われ、乳白色になるんです。
HIPSは、家電製品の外装や玩具、食品容器などに使われています。テレビのケースや冷蔵庫の内部部品など、ある程度の強度が必要な製品に適しています。GPPSと比べて加工もしやすく、大量生産に向いているという特徴があります。
発泡ポリスチレン
発泡ポリスチレンは、ポリスチレンに発泡剤を加えて泡立てたもので、一般的には「発泡スチロール」と呼ばれています。製品の約98%が空気で、残りの2%だけがポリスチレンという、非常に軽い素材です。
発泡ポリスチレンは、断熱性と緩衝性に優れており、食品トレイや梱包材、建築用断熱材として幅広く使われています。軽くて丈夫で、熱を伝えにくいという特性があります。また、切断や加工が簡単で、様々な形状に加工できるんです。
シンジオタクチック
シンジオタクチックポリスチレン(SPS)は、1990年代に開発された新しいタイプのポリスチレンです。分子の配列が規則正しく並んでいることが特徴で、結晶性を持つため、一般的なポリスチレンよりも耐熱性に優れているんですよ。
SPSは、一般的なポリスチレンの耐熱温度が70-90℃であるのに対し、200℃以上の高温にも耐えることができます。そのため、エンジニアリングプラスチック(高性能プラスチック)として、自動車部品や電子部品など、高温環境で使用される製品に使われています。
ポリスチレンの特徴
ポリスチレンが様々な用途で使われている理由となる、基本的な特性を詳しく見ていきましょう。
透明性と光学特性
ポリスチレンの最も優れた特徴の一つが、高い透明性です。光の透過率が90%以上と非常に高く、ガラスに匹敵する透明度を持っています。この透明性により、中身が見える容器や光学部品に適しているんです。
また、屈折率という光の曲がり具合を表す値も1.59と適度な値を持っており、レンズなどの光学製品にも使用されています。最近では、液晶ディスプレイの拡散板や導光板など、電子機器の光学部品としても重要な役割を果たしています。透明性の高さが、現代のデジタル機器を支えていんですよ。
軽量性と比重
ポリスチレンは非常に軽い素材です。比重(水を1とした時の重さの比)は1.04-1.05程度で、水よりもわずかに重い程度です。プラスチックの中でも、ポリプロピレン(比重0.9)、ポリエチレン(比重0.94)に次いで3番目に軽い素材となっています。
この軽量性により、製品の軽量化に大きく貢献しています。例えば、同じ大きさの容器を金属で作る場合と比べて、大幅に軽くすることができるんです。輸送コストの削減や、使用時の取り扱いの改善にもつながっています。軽いということは、環境負荷の軽減にも貢献しているんです。
電気絶縁性
ポリスチレンは電気を通さない性質(電気絶縁性)に優れています。この特性により、電気製品の外装材や絶縁部品として幅広く使用されています。特別な処理を行わなくても、そのまま電気絶縁材料として使用できるのは大きなメリットなんです。
高周波に対する絶縁性も優れており、ラジオやテレビなどの高周波機器にも適しています。電気的な安全性が求められる家電製品において、ポリスチレンの電気絶縁性は重要な役割を果たしています。また、静電気も発生しにくいという特徴もあるんですよ。
成形しやすさ
ポリスチレンは加工性に優れており、様々な成形方法に対応できます。射出成形、押出成形、真空成形など、多くの加工方法で精密な製品を作ることができます。溶融時の流動性が良く、複雑な形状でも綺麗に成形できるのが特徴ですね。
成形時の寸法安定性も優れており、設計通りの正確な寸法の製品を作ることができるんです。また、成形温度も比較的低く、エネルギー効率の良い生産が可能です。この加工のしやすさが、ポリスチレンが様々な製品に使われている理由の一つなんです。
ポリスチレンの長所
ポリスチレンが世界中で広く使われている理由となる、優れた特徴を詳しく見ていきます。
安価な製造コスト
ポリスチレンの最大の長所の一つが、製造コストの安さです。原料となるスチレンモノマーが比較的安価で、製造プロセスも他のプラスチックと比べて簡単なため、大量生産によってコストを抑えることができるんです。
この価格の安さにより、使い捨て容器や梱包材など、コストを重視する用途に適しています。5大汎用樹脂の中でも特にコストパフォーマンスに優れており、大量消費される製品には欠かせない素材となっています[2]。安価でありながら必要な性能を備えているため、経済的な製品作りに貢献しているんです。
優れた透明度
ポリスチレンの透明度は、プラスチックの中でも トップクラスです。光の透過率が90%以上と非常に高く、ガラスに近い透明感を実現できます。この優れた透明性により、中身を美しく見せる容器や、光学用途に使用することができるんですよ。
また、着色も容易で、透明感を保ったまま様々な色に着色することができます。美しい発色と透明感を両立できるため、装飾品や玩具などにも広く使われています。デザイン性を重視する製品において、ポリスチレンの透明性は大きな価値をもたらしているんです。
加工性の良さ
ポリスチレンは成形加工が非常に容易です。溶融温度が比較的低く、流動性が良いため、複雑な形状でも精密に成形することができます。また、成形後の寸法安定性も優れており、設計通りの製品を安定して生産できます。
切削加工や接着も容易で、後加工による製品の改良も可能です。この加工性の良さにより、プロトタイプ(試作品)の製作から大量生産まで、幅広い製造段階で活用されています。製造業にとって扱いやすい素材であることが、普及の大きな要因なんです。
着色の容易さ
ポリスチレンは着色が非常に容易で、鮮やかで美しい色を出すことができるんです。顔料や染料を均一に分散させることができ、透明性を活かした美しい着色製品を作ることができます。色の調整も比較的簡単で、様々な色調を実現できます。
また、メタリック調や パール調など、特殊な効果を持つ着色も可能です。この着色の容易さにより、デザイン性を重視する製品や、色分けが必要な製品に広く使用されています。消費者の多様なニーズに対応できる柔軟性を持っているんですね。

ポリスチレンの短所
優れた特徴を持つポリスチレンですが、いくつかの制限もあります。使用時の注意点を理解しておきましょう。
耐熱性の限界
ポリスチレンの最大の短所は、耐熱性が低いことです。通常使用時の耐熱温度は70-90℃程度で、それ以上の温度では変形したり、性質が変化したりします。そのため、高温になる用途には使用できません。
例えば、電子レンジでの加熱や、熱湯での洗浄などはできません。また、夏場の車内など、高温になる環境での使用にも注意が必要です。この耐熱性の制限により、用途が限定される場合があるんです。使用時には、温度に注意を払うことが重要です。
耐衝撃性の弱さ
一般的なポリスチレン(GPPS)は、衝撃に対して脆く、強い力が加わると割れやすいという欠点があります。特に低温時には、この傾向が顕著になります。落下させたり、強く曲げたりすると、簡単に破損してしまうことがあるんです。
この問題を解決するために、ゴム成分を加えた耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)が開発されましたが、それでも金属などと比べると衝撃強度は劣ります。取り扱い時には、衝撃を与えないよう注意が必要なんです。特に薄い製品では、この特性により破損しやすくなります。
薬品への耐性
ポリスチレンは、有機溶剤(シンナーやアルコール系の薬品)に対して耐性が低く、これらの薬品に触れると溶解したり、白濁したりします。また、油類に対しても抵抗性が低く、長期間接触すると劣化することがあるんですよ。
清拭用のアルコールや、化粧品、香水などに含まれる成分によっても影響を受ける場合があります。そのため、これらの薬品を扱う用途には適していません。使用環境を考慮して、適切な材料選択をすることが重要です。日常使用時も、薬品類との接触は避ける必要があります。
日常生活での用途
私たちの身の回りでポリスチレンがどのように活用されているかを、具体例とともに見ていきます。
食品容器での活用
ポリスチレンは、食品容器として最も身近な用途の一つです。日本では食品包装用途が約6割を占めており、スーパーやコンビニで見かける様々な容器に使用されています[3]。透明で中身が見えやすく、軽量で取り扱いが簡単なことから、食品容器に適しています。
発泡ポリスチレン製の食品トレイは、肉や魚、野菜などの包装に広く使われています。軽量で断熱性があり、食品の鮮度保持に効果があります。また、透明なポリスチレン容器は、お弁当や惣菜の容器として使われ、内容物を美しく見せる効果があります。
家電製品への応用
家電製品の外装材や内部部品にも、ポリスチレンが多用されているんです。テレビのケース、冷蔵庫の内部部品、エアコンの外装など、様々な家電製品に使われています。電気絶縁性に優れているため、安全性が重要な電気製品に適しています。
また、軽量性により製品全体の重量を軽くすることができ、取り扱いや輸送の利便性向上に貢献しています。加工性の良さから、複雑な形状の部品も精密に製造でき、デザイン性の向上にも役立っています。家電製品の進化を支える重要な素材の一つなんです。
学用品での利用
学校や オフィスで使われる文房具にも、ポリスチレンが広く使用されています。透明な定規、筆箱、ファイルケース、CDケースなど、透明性と加工性を活かした製品がたくさんあります。軽量で丈夫、そして安価であることから、学用品に適した素材なんです。
特に透明な製品では、ポリスチレンの高い透明度が活かされているんです。また、着色も容易なため、カラフルな文房具の製造にも使われています。子どもたちが毎日使う身近な製品として、安全性と機能性を両立した素材として重要な役割を果たしています。
建築材料としての役割
建築分野では、主に発泡ポリスチレンが断熱材として使用されています。住宅の壁や屋根、床下に設置され、冷暖房効率の向上に大きく貢献しています。軽量で施工が容易なことから、建築作業の効率化にもつながっているんです。
押出法発泡ポリスチレン(XPS)は、特に高い断熱性能を持ち、住宅の省エネルギー化に重要な役割を果たしています。また、吸水性が低いため、湿気の多い環境でも性能を維持できます。これにより、建物の長寿命化と快適な居住環境の実現に貢献しています。
産業分野での用途
ポリスチレンは、様々な産業分野でも重要な役割を果たしています。専門的な用途を見ていきましょう。
包装材料の分野
産業用の包装材料として、ポリスチレンは幅広く活用されています。精密機器や電子部品の梱包材として、発泡ポリスチレンの優れた緩衝性能が重要な役割を果たしています。軽量でありながら優れた保護機能を提供し、輸送中の破損を防いでいるんですよ。
また、食品の業務用包装材としても使用されており、大容量の容器や業務用トレイなどに使われています。透明性により内容物の確認が容易で、衛生管理にも優れています。コストパフォーマンスの良さから、大量に使用される産業用途に適しているんです。
断熱材としての利用
発泡ポリスチレンは、工業施設や商業施設の断熱材として重要な役割を果たしています。冷凍倉庫や冷蔵施設では、優れた断熱性能により省エネルギー効果を発揮しています。軽量で加工が容易なため、複雑な形状の施設にも対応できるんです。
また、船舶や航空機などの輸送機器でも断熱材として使用されています。軽量性が特に重要な航空機においては、燃費改善に貢献する重要な素材となっています。産業用途では、性能と経済性の両立が求められるため、ポリスチレンの特性が活かされています。
電子部品への応用
電子機器の製造において、ポリスチレンは様々な部品に使用されているんです。絶縁性に優れているため、電子回路の絶縁材や保護材として重要な役割を果たしています。また、軽量性により、携帯機器の軽量化にも貢献しています。
光学特性を活かして、液晶ディスプレイの拡散板や導光板などにも使用されています。これらの部品は、画面の明るさや均一性を向上させる重要な役割を果たしており、現代のデジタル機器には欠かせない部品となっているんです。精密な光学特性が要求される用途においても、ポリスチレンは活躍しています。
自動車業界での活用
自動車業界では、軽量化と安全性の向上を目的として、ポリスチレンが様々な部品に使用されています。内装材や外装部品、緩衝材など、幅広い用途で活用されています。軽量化により燃費改善に貢献し、環境負荷の軽減にもつながっているんです。
特に発泡ポリスチレンは、衝撃吸収材として重要な役割を果たしています。事故時の衝撃を吸収し、乗員の安全を守る重要な部品として使用されています。また、断熱性を活かして、車内の温度管理にも貢献しています。自動車の性能向上と安全性確保に欠かせない素材となっているんですね。
発泡スチロールの特徴
ポリスチレンの中でも特に身近な発泡スチロールについて、その特性と製造方法を詳しく解説します。
製造プロセス
発泡スチロールの製造工程は以下のようになります。まず、ポリスチレンの小さな粒(原料ビーズ)に発泡剤を混ぜ込みます。この原料ビーズの直径は0.3-2mm程度です。
発泡スチロールの製造手順
原料ビーズの準備
発泡剤の混合
予備発泡処理
金型への充填
高温蒸気による本発泡
冷却・固化
製品の取り出し
金型に入れた原料ビーズに高温の蒸気を当てると、発泡剤が気化して膨張し、ビーズ同士がくっついて金型の形になります。この工程により、製品体積の約98%が空気、残り2%がポリスチレンという、非常に軽い製品ができあがります。発泡倍率は通常50倍程度ですが、用途に応じて調整できるんです。
断熱性能の秘密
発泡スチロールの優れた断熱性能は、その構造に秘密があります。無数の小さな気泡が熱の伝導を遮断し、優れた断熱効果を発揮します。空気は熱を伝えにくい性質があるため、98%が空気でできている発泡スチロールは、非常に優れた断熱材になるんです。
この断熱性能により、冷たいものは冷たいまま、温かいものは温かいまま保つことができます。アイスクリームの容器や温かい弁当の容器として使われているのも、この断熱性能があるからです。また、建築用断熱材としても、省エネルギー効果を発揮しているんですよ。
軽量化のメリット
発泡スチロールの軽量性は、様々なメリットをもたらします。同じ体積の水と比べて約50分の1という軽さは、輸送コストの大幅な削減につながります。また、使用時の取り扱いも容易になり、作業効率の向上にも貢献しています。
この軽量性は、省資源という観点からも重要です。少ない原料で大きな製品を作ることができるため、資源の有効活用につながります。環境負荷の軽減という観点からも、発泡スチロールの軽量性は重要な特徴なんです。
緩衝材としての機能
発泡スチロールは、優れた緩衝性能を持っています。衝撃を受けた時に、内部の気泡が変形することで衝撃を吸収し、保護対象物を守ります。この特性により、精密機器や壊れやすい物品の梱包材として重要な役割を果たしています。
また、復元性にも優れており、一度変形しても元の形に戻る性質があります。この特性により、繰り返し使用することも可能です。軽量でありながら優れた保護機能を提供することから、輸送業界では欠かせない材料なんですよ。
5大汎用樹脂の位置づけ
ポリスチレンがプラスチック業界でどのような位置にあるのかを、他の樹脂との比較で見ていきます。
汎用樹脂とは何か
汎用樹脂とは、大量生産され、安価で日常的に使用されるプラスチックのことです。特別な性能よりも、コストパフォーマンスと使いやすさを重視した樹脂群です。5大汎用樹脂には、ポリスチレン以外にポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレンテレフタレートが挙げられます。
これらの樹脂は、それぞれ異なる特徴を持ちながら、私たちの生活を支える基盤となっているんです。汎用樹脂は、エンジニアリングプラスチック(高性能プラスチック)と区別され、より一般的で身近な用途に使用されています。コストと性能のバランスが取れた実用的な素材群です。
他樹脂との比較
5大汎用樹脂の特徴は以下のようになります。それぞれに独自の特性があり、用途によって使い分けられています。
ポリエチレン:柔軟で耐薬品性に優れる
ポリプロピレン:軽量で耐熱性がある
ポリスチレン:透明で硬い
ポリ塩化ビニル:耐候性に優れる
PET:透明で強度が高い
ポリスチレンは、この中でも特に透明性と加工性に優れており、光学用途や精密部品に向いているんです。一方で、耐熱性や耐衝撃性では他の樹脂に劣る面もあります。それぞれの樹脂が持つ特性を理解し、用途に応じて適切に選択することが重要です。
市場シェアと需要
世界のポリスチレン市場は年間約1200万トンの規模があり、5大汎用樹脂の中でも重要な位置を占めています[4]。日本国内では年間約65-70万トンが使用されており、その約6割が食品包装用途となっています。
地域別に見ると、アジア太平洋地域が最大の消費地域となっており、経済成長とともに需要が拡大しています。用途別では、包装材料が最大の用途で、次いで建材、電子機器となっています。市場の成熟化とともに、リサイクル技術の向上や環境対応が重要なテーマとなっています。
安全性と食品への利用
食品容器として広く使用されているポリスチレンの安全性について詳しく解説します。
食品容器での安全基準
ポリスチレンは、世界各国の食品安全基準をクリアした安全な材料です。日本では食品衛生法に基づく規格基準に適合しており、食品と直接接触する容器として使用が認められています。溶出試験などの厳格な試験をクリアしており、安全性が確認されています。
製造時には、残留モノマー(未反応のスチレン)の量が厳しく管理されており、食品に移行する可能性のある物質は安全なレベルに抑えられています。定期的な品質管理と安全性の確認により、消費者が安心して使用できる品質が保たれています。
無味無臭の特性
ポリスチレンは無味無臭の特性を持っており、食品の味や香りに影響を与えません。この特性により、食品本来の味を損なうことなく包装することができます。特に繊細な味の食品や香りの強い食品でも、品質を保持できるんです。
ただし、長期間の保存や高温での使用は避ける必要があります。適切な使用条件下では、食品の品質を保持し、安全に使用することができます。食品メーカーも、この特性を活かしてさまざまな食品の包装に活用しています。
各国での承認状況
ポリスチレンは、アメリカのFDA(食品医薬品局)、ヨーロッパのEFSA(欧州食品安全機関)、日本の厚生労働省など、世界の主要な食品安全機関で承認されています。国際的に安全性が認められた材料として、グローバルに使用されているんです。
各国の基準は微細な部分で違いがありますが、基本的な安全性については共通の認識があります。国際貿易においても、ポリスチレン製の食品容器は広く流通しており、国際基準としての安全性が確立されています。継続的な安全性の評価と改善により、今後も安全な使用が期待されているんですよ。
環境への配慮
環境問題が注目される今、ポリスチレンの環境配慮とリサイクルの取り組みを詳しく見ていきます。
リサイクルの現状
日本では年間約97万トンのポリスチレンが廃棄され、そのうち約15万トン(約8%)がマテリアルリサイクルされています[5]。特に発泡ポリスチレン製の食品トレイは、スーパーマーケットの店頭回収により高いリサイクル率を実現しているんです。
リサイクルの種類は大きく3つに分けられます。マテリアルリサイクル(物質として再利用)、ケミカルリサイクル(化学的に分解して原料に戻す)、エネルギーリカバリー(燃料として利用)です。ポリスチレンは、これらすべてのリサイクル方法に対応できる優れた特性を持っています。
マテリアルリサイクル
マテリアルリサイクルは、使用済みのポリスチレンを溶かして、再び新しい製品に作り変える方法です。ポリスチレンは熱をかけても性質が変化しにくいため、マテリアルリサイクルに適した材料です。特に単一素材で作られた製品は、高品質なリサイクルが可能なんです。
発泡ポリスチレンの食品トレイは、「トレーtoトレー」というリサイクルシステムにより、回収されたトレイが再び食品トレイとして生まれ変わります。この循環システムにより、資源の有効活用と廃棄物の削減を同時に実現しています。消費者の分別協力により、このシステムが成り立っているんですよ。
ケミカルリサイクル
ケミカルリサイクルは、使用済みポリスチレンを化学的に分解して、元の原料であるスチレンモノマーに戻す技術です。この方法により、着色されたものや汚れがついたものでも、新品同等の品質の原料として再生できます。
ポリスチレンは熱分解しやすい性質があるため、ケミカルリサイクルに適した材料です。近年、この技術の実用化が進んでおり、将来的には完全循環型のリサイクルシステムの実現が期待されています。技術の進歩により、リサイクル率のさらなる向上が見込まれているんですね。
廃棄時の注意点
ポリスチレン製品を廃棄する際は、適切な分別が重要です。まず、汚れを取り除き、他の材料と分けて排出する必要があります。特に食品容器は、残った食べ物をきれいに取り除いてから分別することが大切なんです。
地域によって分別ルールが異なるため、お住まいの自治体の分別方法を確認することが重要です。適切な分別により、リサイクル率の向上と環境負荷の軽減につながります。一人ひとりの行動が、循環型社会の実現に貢献するんです。

まとめ
ポリスチレンは、私たちの生活に欠かせない重要なプラスチック素材です。透明性、軽量性、加工性に優れ、食品容器から家電製品まで幅広い用途で活用されています。5大汎用樹脂の一つとして、安価でありながら必要な性能を備えた実用的な材料として、80年以上にわたって私たちの生活を支えてきました。
一方で、環境問題への対応も重要な課題なんです。適切な分別とリサイクルにより、資源の有効活用と環境負荷の軽減を図ることができます。マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルの技術向上により、循環型社会の実現に向けた取り組みが進んでいます。私たち一人ひとりが正しい知識を持ち、適切な分別を行うことで、持続可能な社会の実現に貢献できるんです。ポリスチレンについて理解を深め、環境に配慮した使い方を心がけていきましょう。
お知らせ
最後まで、読んでいただき光栄です。私たち都市環境サービスは、プラスチックリサイクルに特化した会社です。フラフ燃料の製造や代替燃料に興味がある方、リサイクルの会社で働いてみたい方は、こちらのフォームから気軽にお問合せください。よろしくお願いします。

出典: