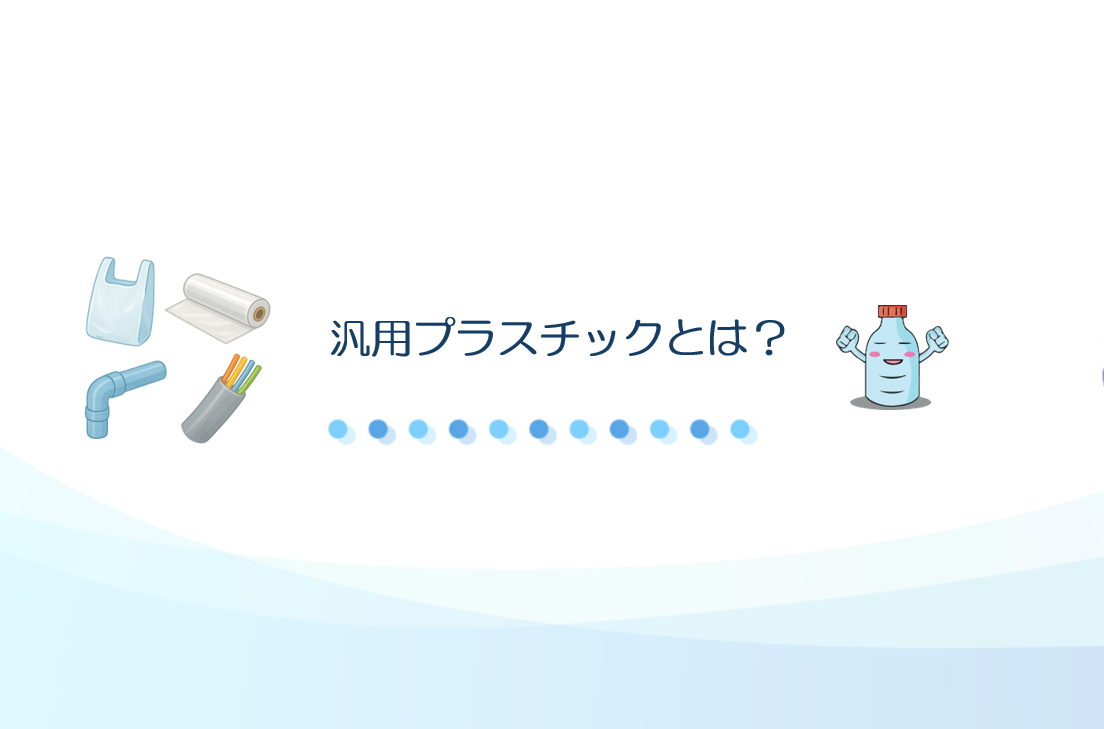皆さんこんにちは。都市環境サービスの前田です。今回のテーマは「汎用プラスチックの種類と用途」です。スーパーのレジ袋やペットボトル、お弁当のトレイなど、私たちの周りにあふれているプラスチック製品、その材料の違いって気になったことはありませんか?

実は、身の回りのプラスチック製品の約8割は「汎用プラスチック」と呼ばれる5つの材料でできているんです[1]。これらの材料を知ることで、製品選びや仕事での材料選択がもっと上手になるんですよ。本記事では、汎用プラスチックの基本から用途別の選び方まで、専門知識がなくても理解できるよう詳しく解説していきます。
目次は以下の通りです。
①汎用プラスチックの基礎知識
②代表的な5つの汎用プラスチック
③材料ごとの性能と特徴比較
④使い道別の材料の選び方
⑤プラスチック製品の作り方
⑥汎用プラスチックの良い点
⑦知っておきたい問題点
汎用プラスチックは私たちの生活を支える重要な材料なんです。ぜひ最後までご一読ください。
汎用プラスチックの基礎知識
まずは汎用プラスチックがどのような材料なのか、基本的なことから学んでいきましょう。
汎用プラスチックとは何か
汎用プラスチックとは、私たちの身の回りで最もよく使われている一般的なプラスチック材料のことです。「汎用」という言葉が示すように、幅広い用途に使える材料という意味なんですね。
この材料の最大の特徴は、熱を加えると柔らかくなって形を変えることができる性質です。冷やすと再び固くなるので、何度でも形を変えることができるんです。これを「熱可塑性」と呼びます。
日本で作られるプラスチック製品の約8割が汎用プラスチックでできています[1]。レジ袋、ペットボトル、食品トレイ、タッパーなど、本当に身近な製品ばかりなんですよ。
エンプラとの基本的な違い
プラスチックには汎用プラスチック以外にも「エンジニアリングプラスチック(エンプラ)」という種類があります。この2つの違いを知っておくと、材料の特徴がよくわかるんです。
最も大きな違いは温度に対する強さです。汎用プラスチックは100℃程度で変形し始めますが、エンプラは150℃以上でも形を保つことができます。つまり、汎用プラスチックはお湯程度の温度でも変形してしまうということなんですね。
ただし、汎用プラスチックには大きなメリットもあります。値段が安くて、加工がしやすいんです。エンプラは高性能ですが、価格が高くて加工も複雑になります。日用品には汎用プラスチック、高温になる機械部品にはエンプラというように使い分けられているんですよ。
代表的な5つの汎用プラスチック
汎用プラスチックは主に5つの種類に分かれています。それぞれの特徴と身近な用途を見ていきましょう。
ポリエチレン(PE)
ポリエチレンは世界で最も多く作られているプラスチック材料です[2]。略号「PE」で表記されることも多く、身の回りの製品によく使われています。
ポリエチレンは密度によって2つの種類に分かれています。以下になります。
・高密度PE(硬くて丈夫)
・低密度PE(柔らかくて透明)
高密度PEは洗剤のボトルやバケツなど、ある程度の強度が必要な製品に使われます。一方、低密度PEはレジ袋やラップフィルムなど、薄くて柔軟な製品に適しているんです。どちらも化学物質に強く、水に浮くほど軽い材料です。最大のメリットは原料が安いことで、大量生産に向いているんですよ。
ポリプロピレン(PP)
ポリプロピレンは汎用プラスチックの中で最も熱に強い材料です。100℃近くまで耐えることができるので、電子レンジで温める容器などに使われています。
この材料の特徴は軽さと丈夫さのバランスが良いことです。ポリエチレンよりもさらに軽く、水に浮きますが、強度はしっかりあります。そのため、自動車の内装部品にも広く使われているんです。
身近な製品としては、タッパーなどの食品保存容器、洗剤やシャンプーのボトル、ストローなどがあります。透明度もそこそこ高く、着色もしやすいので、カラフルな日用品によく見かけますよね。ただし、低温では割れやすくなるという弱点もあります。
ポリ塩化ビニル(PVC)
ポリ塩化ビニルは「塩ビ」の名前で親しまれている材料です。最大の特徴は燃えにくく、長持ちすることです。そのため建物の配管や外壁材など、安全性と耐久性が重要な場所でよく使われています。
表面にツヤがあって、透明から不透明まで自由に作ることができます。また、添加剤を加えることで、硬いものから柔らかいものまで幅広い硬さに調整できるんです。
身近な用途では、水道管、雨どい、床材、クレジットカードなどがあります。病院で使う血液バッグや点滴チューブにも使われていて、私たちの安全を守る重要な材料なんですよ。ただし、燃やすと有害なガスが出る可能性があるため、廃棄には注意が必要です。
ポリスチレン(PS)
ポリスチレンは軽くて断熱効果が高い材料です。最も身近な例は発泡スチロールですね。発泡スチロールは、ポリスチレンに気泡をたくさん作って軽くした材料なんです。
普通のポリスチレンは透明で、硬くて光沢があります。加工がしやすく、細かい模様も作ることができます。ただし、衝撃に弱くて割れやすいという弱点があります。
身近な製品では、CDやDVDのケース、使い捨てのコップや皿、食品トレイなどに使われています。発泡スチロールは魚箱や宅配便の緩衝材、住宅の断熱材として活躍しています。軽くて断熱性が高いので、省エネにも貢献している材料なんですよ。
PET樹脂
PET樹脂は正式名称を「ポリエチレンテレフタレート」といいます。最も身近な例はペットボトルですね。透明で美しく、化学物質に強い特徴があります。
この材料の優秀な点は、ガスを通しにくいことです。そのため炭酸飲料のボトルにも使われています。また、繊維にもなるので、ポリエステルの服の原料でもあるんです。
ペットボトル以外では、食品の包装フィルム、卵パック、薬の包装などに使われています。透明度が高く、食品の中身がよく見えるのもメリットです。リサイクルもしやすく、回収されたペットボトルは新しいペットボトルや服に生まれ変わることができるんですよ。

材料ごとの性能と特徴比較
5つの汎用プラスチックにはそれぞれ得意分野があります。性能を比較して使い分けのポイントを理解しましょう。
熱への強さの違い
汎用プラスチックを選ぶ際に重要なのが、どれくらいの温度まで耐えられるかということです。使う場所の温度に合わせて材料を選ぶ必要があるんです。
各材料の耐熱温度は以下になります。
PE:80-90℃
PP:100-120℃
PVC:60-80℃
PS:70-90℃
PET:70-80℃
ポリプロピレンが最も熱に強く、電子レンジ対応の容器によく使われる理由がわかりますね。一方、PVCは意外に熱に弱いのですが、添加剤によって改良されることが多いんです。お湯を入れる用途では、必ず耐熱温度を確認することが大切ですよ。
強度と丈夫さの比較
プラスチックの強度は用途によって重要度が変わります。壊れやすいものは安全性に関わることもあるので、しっかり理解しておきましょう。
引っ張りに対する強さでは、PETとPVCが優秀です。フィルムや薄い製品でも破れにくいんですね。曲げに対してはPPが強く、何度も曲げ伸ばししても折れにくい特徴があります。
衝撃を受けたときの強さでは、PEとPPが優れています。落としても割れにくいので、容器類によく使われるんです。一方、PSとPVCは衝撃に弱く、特にPSは低温で割れやすくなります。用途に応じて、必要な強度を満たす材料を選ぶことが重要なんですよ。
化学的な性質の違い
プラスチックが化学物質にどれくらい強いかは、特に容器や配管材料では重要な性能です。材料によって得意不得意があるんです。
酸やアルカリに対する強さでは、PEとPPが優秀です。化学工場の配管や薬品容器によく使われる理由ですね。PVCも化学物質には比較的強いのですが、一部の有機溶剤には弱い面があります。
紫外線への強さでは、材料によって大きな差があります。PVCとPETは比較的強く、屋外での使用に向いています。一方、PEとPSは紫外線で劣化しやすいので、屋外で使う場合は紫外線防止剤を添加することが多いんです。食品と接触する用途では、すべての汎用プラスチックが安全基準を満たしているので安心して使えますよ。
使い道別の材料の選び方
実際に材料を選ぶときは、どんな用途に使うかを考えることが大切です。用途別の選び方のコツを見ていきましょう。
包装や容器に使う場合
食品包装や容器では、安全性と保存性が最も重要です。食品の種類や保存期間によって適した材料が変わってくるんです。
液体を入れる容器では、PETとPEがよく使われます。PETは透明で中身が見やすく、炭酸ガスも逃げにくいので炭酸飲料に最適です。PEは柔らかくて落としても割れにくいので、調味料のボトルなどに向いています。
フィルム包装では、用途によって材料を使い分けます。レジ袋やゴミ袋には安価なPE、冷凍食品の包装には低温でも丈夫なPP、お菓子の包装には透明度の高いPSやPETが選ばれることが多いんです。電子レンジ対応が必要な場合は、必ずPPを選ぶことが重要ですよ。
車の部品として使う場合
自動車では軽量化と耐久性の両立が求められます。また、部品の取り付け場所によって要求される性能も大きく変わってくるんです。
内装部品では、PPが最も多く使われています[3]。軽くて加工しやすく、ある程度の耐熱性もあるからです。ダッシュボード、ドアトリム、シートの一部などに広く使われています。着色も自由なので、内装の色合わせも簡単なんですね。
エンジンルーム周辺では温度が高くなるため、汎用プラスチックの使用は限定的です。それでも、エアクリーナーボックスやリザーバータンクなど、直接高温にならない部品にはPPが使われることがあります。燃料タンクには特殊な多層構造のPEが使われていて、ガソリンが漏れないように工夫されているんですよ。
建物の材料として使う場合
建築材料では長期間の耐久性と安全性が何よりも重要です。特に配管材料では、漏水事故を防ぐために慎重な材料選択が必要なんです。
水道管には主にPVCが使われています。化学物質に強く、錆びることがないからです。また、燃えにくいという性質も建築材料として重要なポイントです。継手類も同じPVCで作られるので、接続も確実にできるんですね。
外壁材や屋根材では、紫外線や雨風に強い材料が必要です。PVCは屋外での耐久性が高いので、雨どいや外壁サイディングによく使われます。断熱材としては発泡PSが使われることもありますが、最近は防火性能がより高い材料に置き換わってきているんですよ。
電気製品の部品として使う場合
電気製品では安全性が最優先です。電気を通さないこと、燃えにくいこと、有害なガスを出さないことが重要な条件になります。
電気を通さない性能では、すべての汎用プラスチックが優秀です。ただし、湿気を吸いやすい材料は電気特性が悪くなることがあるので注意が必要です。PEとPPは湿気をほとんど吸わないので、電気部品のケースによく使われています。
燃えにくさでは、PVCが最も優秀です。電線の被覆材や配電盤のケースなど、火災安全が重要な部品に使われています。PSやPEは燃えやすいので、電気製品では難燃剤を添加することが多いんです。精密部品では寸法の安定性も重要で、PETやPVCが温度変化による変形が少ないため選ばれることが多いんですよ。
プラスチック製品の作り方
汎用プラスチックがどのように製品になるのか、主な製造方法を知っておくと材料選択にも役立ちます。
射出成形という方法
射出成形は最も一般的なプラスチック製品の作り方です。溶かしたプラスチックを金型に圧力をかけて流し込み、冷やして固める方法なんです。
この方法の利点は以下になります。
複雑な形も作れる
大量生産に向いている
寸法精度が高い
表面がきれいに仕上がる
タッパー、おもちゃ、電子機器のケースなど、私たちの身の回りの製品の多くが射出成形で作られています。各材料によって溶かす温度や圧力が違うので、材料に合わせて条件を調整する必要があります。PPやPEは比較的低い温度で成形でき、PVCは温度管理が特に重要になるんですよ。
押出成形という方法
押出成形は、溶かしたプラスチックを連続的に押し出して、フィルムやシート、パイプなどを作る方法です。ところてんを作るときのように、型から連続的に材料が出てくるイメージですね。
この方法で作られる製品は以下になります。
レジ袋(PEフィルム)
ラップフィルム(PE)
水道管(PVC)
電線被覆(PE、PVC)
押出成形の最大のメリットは、長い製品を効率よく作れることです。フィルムなら何百メートルも連続して作ることができます。材料の流れやすさが重要で、PEやPPは押出成形に適していますが、PSは少し難しい材料とされているんですよ。

ブロー成形という方法
ブロー成形は中が空っぽの容器を作るための方法です。風船を膨らませるように、プラスチックに空気を吹き込んで容器の形にする技術なんです。
ブロー成形で作られる代表的な製品は以下になります。
ペットボトル(PET)
洗剤ボトル(PE、PP)
シャンプーボトル(PE)
ガソリンタンク(PE)
この方法の利点は、継ぎ目のない丈夫な容器が作れることです。特にペットボトルは、PETの透明性と強度を活かした代表的な製品ですね。材料によって膨らませる温度や圧力が違い、PETは高温でないとうまく膨らまないため、専用の設備が必要になります。大型の容器も作ることができるので、自動車の燃料タンクにも使われているんですよ。
汎用プラスチックの良い点
汎用プラスチックが世界中で広く使われているのには、たくさんの理由があります。その魅力を詳しく見てみましょう。
お金の面でのメリット
汎用プラスチックの最大の魅力は、なんといっても安価なことです。原料となる石油由来の化学物質が比較的安く手に入るうえ、製造技術も確立されているからなんです。
特に大量生産では、そのコストメリットがさらに大きくなります。金型を一度作ってしまえば、何万個、何十万個でも同じ品質で作り続けることができるんです。人件費も安く抑えられるので、日用品を手頃な価格で提供できているんですね。
また、加工に必要なエネルギーも少なくて済みます。金属のように高温で溶かす必要がないため、電気代やガス代も節約できます。これらのコストダウンが最終的に製品価格に反映されて、私たち消費者にとって手に取りやすい価格になっているんですよ。
加工しやすさのメリット
汎用プラスチックは加工のしやすさでも優れています。熱を加えるだけで柔らかくなるので、複雑な形でも比較的簡単に作ることができるんです。
成形後の加工も自由度が高いのが特徴です。切る、削る、穴を開ける、溶接するなど、様々な加工方法が使えます。接着剤もよく効くので、複数の部品を組み合わせることも簡単です。
色をつけることも簡単で、透明から不透明まで、ほぼどんな色でも作ることができます。表面に模様をつけたり、文字を印刷したりすることも可能です。金属では難しい装飾も、プラスチックなら手軽にできるんです。この加工の自由度が、デザイン性の高い製品を安価で作ることを可能にしているんですよ。
実用面でのメリット
日常使いでの汎用プラスチックの利便性は本当に高いんです。まず軽いことが大きなメリットですね。ガラスや金属と比べて重量が3分の1から5分の1程度なので、持ち運びが楽になります。
丈夫さも見た目以上に優秀です。落としても割れにくく、ある程度の衝撃なら問題ありません。また、錆びることがないので、水回りでも安心して使えます。化学物質にも強いので、洗剤や薬品を入れる容器としても活躍しているんです。
お手入れが簡単なのも嬉しいポイントです。水で洗うだけできれいになりますし、汚れがこびりついても表面が滑らかなので落としやすいんです。食器洗い機にも対応している製品が多く、忙しい現代生活にとって本当に便利な材料なんですよ。
知っておきたい問題点
便利な汎用プラスチックですが、使用する上で知っておくべき問題点もあります。正しく理解して上手に付き合いましょう。
性能面での限界
汎用プラスチックの最大の弱点は熱に弱いことです。100℃程度で変形し始めるので、高温になる場所では使えません。沸騰したお湯を直接かけたり、火の近くに置いたりすると変形してしまうんです。
機械的な強度にも限界があります。金属のように重いものを支えたり、強い力がかかる部分には向いていません。特に低温では脆くなりやすく、冬の屋外などでは割れやすくなる材料もあります。
紫外線による劣化も注意が必要です。長時間日光に当たると色が変わったり、もろくなったりすることがあります。屋外で使用する場合は、紫外線防止剤が添加された製品を選ぶか、定期的な交換が必要になることを覚えておきましょう。
環境面での課題
汎用プラスチックの環境問題は現代社会の大きな課題です[4]。最も深刻なのは、自然環境では分解されにくいことです。土に埋めても何十年も形を保ったままになってしまうんです。
燃やして処理する場合も問題があります。石油を原料としているため、燃焼時にCO2が発生して地球温暖化の原因になります。また、燃やし方が適切でないと有害なガスが発生する可能性もあるんです。
海洋プラスチック問題も深刻です。適切に処理されなかったプラスチックが海に流れ込み、マイクロプラスチックとなって生態系に影響を与えています。私たち一人一人が責任を持って使用し、適切に処理することが重要なんですよ。
まとめ
汎用プラスチックの世界はいかがでしたでしょうか。身の回りにあふれている製品の材料について、これまでより深く理解していただけたと思います。PE、PP、PVC、PS、PETという5つの材料は、それぞれに特徴があり、私たちの生活を支える重要な役割を果たしているんですね。
材料選択では、用途に応じた性能とコストのバランスが重要です。熱への強さ、機械的強度、化学的性質を理解して、最適な材料を選ぶことで、より良い製品作りができるはずです。また、環境問題への配慮も忘れてはいけません。リサイクルや新材料の活用を通じて、持続可能な社会の実現に貢献していくことが求められています。
あなたも今日から、手に取るプラスチック製品の材料に注目してみてください。製品の底面にある「PE」「PP」などの表示を確認することから始めましょう。材料を知ることで、より賢い製品選択ができるようになり、環境にも配慮した生活を送ることができるはずです。
お知らせ
最後まで、読んでいただき光栄です。私たち都市環境サービスは、プラスチックリサイクルに特化した会社です。フラフ燃料の製造や代替燃料に興味がある方、リサイクルの会社で働いてみたい方は、こちらのフォームから気軽にお問合せください。よろしくお願いします。

出典: