皆さんこんにちは。都市環境サービスの前田です。今回のテーマは「産業廃棄物」です。会社で働いている皆さん、オフィスや工場から出るゴミがどのように処理されているか考えたことはありませんか?

実は会社から出るゴミは、家庭のゴミとは全く違う扱いをしなければならないんです。適切に処理しないと法律違反になってしまいます!本記事では、産業廃棄物について、基本的な知識から正しい処理方法まで詳しく解説していきます。
目次は以下の通りです。
①産業廃棄物って何?
②20種類のゴミを覚えよう
③危険な産業廃棄物
④普通のゴミとの見分け方
⑤ゴミ処理の手順
⑥マニフェスト伝票
⑦処理費用の目安
⑧正しい処理のコツ
⑨ルール違反の罰則
産業廃棄物って何?
産業廃棄物は、会社などの事業活動から出る特別なゴミのことなんです。普通の家庭ゴミとは違って、法律でしっかりと定められた特別なルールがあります。
どんなに少量でも産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物のことです。これは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」という法律で決められているんですよ。
ここで重要なのは、どんなに少量でも産業廃棄物は産業廃棄物だということです。個人事業者のように事業規模が小さくても、たった一握りの量でも、法律で決められた20種類に該当すれば産業廃棄物として適切に処理しなければなりません。
どんなに少量でも産業廃棄物
また、産業廃棄物を排出した事業者には「排出事業者責任」という重い責任があります。これは、ゴミを出した会社が最後の最後まで責任を持つということなんです。処理業者に委託したからといって、責任がなくなるわけではありません。
事業活動というのは、製造業や建設業だけでなく、オフィスワークや商店での商業活動、学校などの公共事業も含まれます。つまり、どんな会社や組織でも産業廃棄物と無関係ではいられないんですね。
廃棄物処理法では、まず産業廃棄物を明確に定義して、それ以外のものを一般廃棄物としています。この区別を間違えると法律違反になってしまうので、しっかりと理解しておくことが大切です。
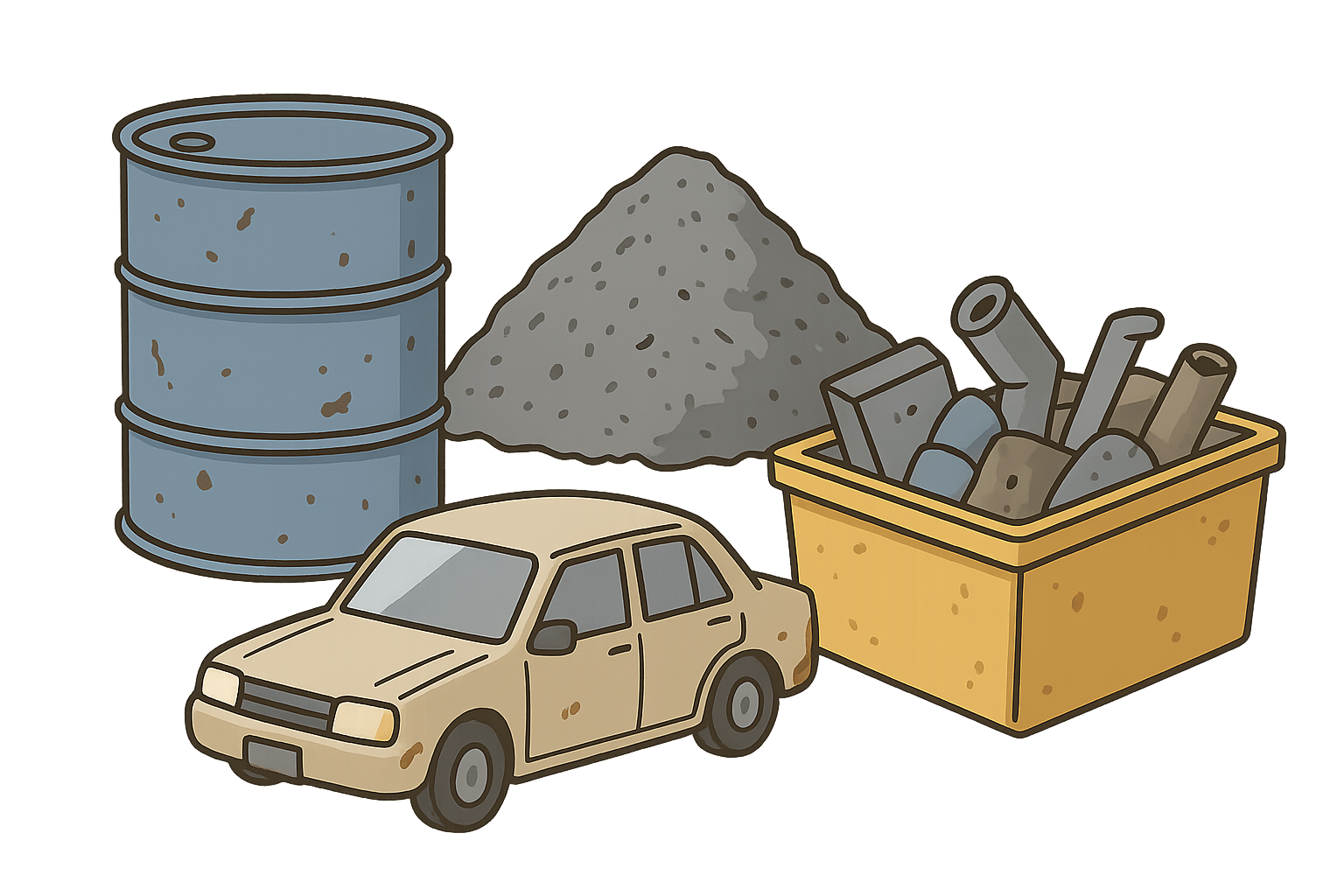
20種類のゴミを覚えよう
産業廃棄物は法律で20種類に分けられています。これらを正しく理解することで、会社のゴミを適切に分別できるようになります。
どの会社でも該当する12種類
まず、業種に関係なくどの会社でも産業廃棄物として扱わなければならない12種類があります。これらは事業の内容に関わらず、排出すれば必ず産業廃棄物になります。
どの会社でも該当する産業廃棄物の種類は以下になります。
・燃えがら(石炭の灰など)
・汚泥(工場の排水処理で出る泥)
・廃油(機械油や食用油)
・廃酸(酸性の廃液)
・廃アルカリ(アルカリ性の廃液)
・廃プラスチック類
・ゴムくず
・金属くず
・ガラスくず・陶磁器くず
・鉱さい(鉱業の廃石など)
・がれき類(コンクリート片など)
・ばいじん(集じん装置で集めた粉じん)
これらの中でも特に身近なのは、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずなどです。オフィスで使っているプラスチック製品が壊れた場合や、金属製の什器を廃棄する際には、これらの産業廃棄物として処理する必要があります。

特定の業種だけの8種類
残りの8種類は、特定の業種から排出された場合のみ産業廃棄物となります。同じ種類のゴミでも、業種によって産業廃棄物になったり一般廃棄物になったりするんです。
特定業種のみ該当する産業廃棄物の種類は以下になります。
・紙くず(建設業・製紙業など)
・木くず(建設業・木材業など)
・繊維くず(建設業・繊維業など)
・動植物性残さ(食品製造業など)
・動物系固形不要物(畜産業など)
・動物のふん尿(畜産業)
・動物の死体(畜産業など)
・処理したもの(上記を処理したもの)
例えば、建設現場で出る木材は産業廃棄物の「木くず」ですが、一般的なオフィスで出る木製品は事業系一般廃棄物になります。また、印刷会社から出る紙は産業廃棄物の「紙くず」ですが、普通のオフィスから出るコピー用紙は事業系一般廃棄物として扱われます。この違いをしっかりと覚えておくことが重要です。

危険な産業廃棄物
産業廃棄物の中でも、特に危険性の高いものは「特別管理産業廃棄物」として厳格に管理されています。
特別管理産業廃棄物とは
代表的な特別管理産業廃棄物としては、廃油の中でも揮発油類や灯油類、強酸性の廃酸(pH2.0以下)、強アルカリ性の廃アルカリ(pH12.5以上)があります。また、アスベスト(石綿)を含む廃石綿等、PCB(ポリ塩化ビフェニル)に汚染された汚泥や廃プラスチック類なども該当します。
医療関係機関から排出される感染性廃棄物も特別管理産業廃棄物の一つです。注射針や血液の付着したガーゼなど、感染の危険性があるものは特別な処理が必要になります。
通常の産廃処理業者では処理できない
これらの特別管理産業廃棄物を扱う場合は、通常の産業廃棄物処理業者では処理できません。特別管理産業廃棄物の許可を持った専門の業者に委託する必要があります。
また、マニフェスト(管理票)の確認期間も通常の90日から60日に短縮されるなど、より厳格な管理が求められるんです。
普通のゴミとの見分け方
産業廃棄物と一般廃棄物の違いを正しく理解することで、適切な処理方法を選択できるようになります。
会社のゴミの分け方
事業活動から出るゴミは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物の2つに分かれます。同じオフィスから出るゴミでも、種類によって扱いが変わるんです。
例えば、オフィスから出る金属製のロッカーは産業廃棄物の「金属くず」になりますが、従業員が持参したお弁当の容器は事業系一般廃棄物になります。また、会社で使っていたプラスチック製のファイルケースは産業廃棄物の「廃プラスチック類」ですが、従業員が飲んだペットボトルは事業系一般廃棄物として扱われます。
紙ゴミの判断は特に注意が必要です。一般的なオフィスから出るコピー用紙や雑誌は事業系一般廃棄物ですが、印刷会社や製紙会社、建設現場から出る紙くずは産業廃棄物になります。業種によって同じ紙でも扱いが変わるので、自社の業種をしっかりと確認することが大切です。
誰が処理するかの違い
産業廃棄物と一般廃棄物では、処理の責任者と管轄する行政機関が違います。これを理解することで、正しい処理ルートを選択できます。
産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。つまり、ゴミを出した会社が最後まで責任を持たなければならないということです。一方、一般廃棄物の処理責任は市町村にあります。ただし、事業系一般廃棄物については、排出事業者が処理責任を負う場合が多いんです。
許可を出す行政機関も違います。産業廃棄物処理業の許可は都道府県知事または政令指定都市の市長が出しますが、一般廃棄物処理業の許可は市町村長が出します。そのため、産業廃棄物は都道府県をまたいでの処理が可能ですが、一般廃棄物は原則として市町村内での処理となります。これにより、産業廃棄物の方が処理ルートの選択肢が多くなる傾向があります。
ゴミ処理の手順
産業廃棄物の処理は、適切な手順を踏むことで環境を守り、法令違反を防ぐことができます。
正しい分け方と保管
産業廃棄物を適切に分別し、正しく保管することは処理の第一歩です。混合廃棄物になると処理費用が高くなってしまうので、しっかりと分別することが重要なんです。
産業廃棄物の分別方法は以下になります。
・種類ごとに分ける
・混ぜると危険なものは分離
・液体と固体を分ける
・有価物は別にする
・特別管理産業廃棄物は隔離
保管についても法律で基準が決められています。保管場所の周囲には囲いを設置し、産業廃棄物の保管場所であることを示す掲示板を設置しなければなりません。また、廃棄物が飛散・流出しないよう適切な措置を講じる必要があります。雨水の侵入を防ぎ、地下水汚染を防止するための対策も必要です。保管できる量や期間にも制限があるので、定期的に処理業者に引き渡すことが大切です。
業者による回収
産業廃棄物の収集運搬は、都道府県知事の許可を受けた専門業者に委託する必要があります。適切な業者選びが重要なポイントになります。
収集運搬業者に求められる条件は以下になります。
・適正な許可証の保有
・取り扱い品目の確認
・保険加入の有無
・実績と信頼性
・適正な価格設定
収集運搬時には、廃棄物が飛散・流出しないよう適切な容器や車両を使用します。運搬車には「産業廃棄物収集運搬者」の表示と、会社名や許可番号を明記する必要があります。また、マニフェストや許可証の写しなど、必要な書類を携行することが義務付けられています。運搬ルートや時間帯についても、周辺環境への配慮が必要です。
処理場での最終処理
収集運搬された産業廃棄物は、中間処理を経て最終処分されます。この過程で廃棄物の減量化やリサイクルが行われるんです。
中間処理の主な方法は以下になります。
・焼却(燃やして減量化)
・破砕(細かく砕く)
・脱水(水分を除去)
・選別(種類別に分ける)
・中和(酸性やアルカリ性を中和)
中間処理により、産業廃棄物の約半分が再利用可能な資源に生まれ変わります。例えば、廃プラスチックはペレット化されて新しいプラスチック製品の原料になり、金属くずは精錬されて新しい金属製品に利用されます。
中間処理で再利用できなかった残りは、最終処分場で埋立処分されたり、海洋投入処分(現在は原則禁止)されたりします。最終処分場では、環境への影響を最小限に抑えるため、厳格な管理が行われています。
マニフェスト伝票
マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、産業廃棄物が適正に処理されたことを確認するための重要な書類です。
紙の管理票の使い方
紙マニフェストは7枚複写式の伝票で、産業廃棄物の流れを追跡管理するシステムです。排出事業者から処分業者まで、各段階で適切に運用する必要があります。
紙マニフェストの流れは以下になります。
・排出事業者がA票を保管
・B1・B2票が収集運搬業者へ
・C1・C2票が処分業者へ
・D・E票も処分業者へ
・各段階で控えを返送
まず排出事業者が必要事項を記入してA票を手元に残し、残りを収集運搬業者に渡します。収集運搬が完了すると、業者はB1票を保管し、B2票を10日以内に排出事業者に返送します。
処分業者での処理が完了すると、C1票を保管し、C2票を処分業者から排出事業者に返送されます。最終処分が完了するとD票、E票も同様に管理され、排出事業者は全ての処理が完了したことを確認できます。
電子版の便利さ
電子マニフェストは、インターネットを利用したマニフェスト管理システムです。紙の管理票に比べて多くのメリットがあります。
電子マニフェストのメリットは以下になります。
・ペーパーレス化
・自動計算機能
・期限管理の自動化
・データの一元管理
・報告書の自動作成
電子マニフェストを利用するには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が全て公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の電子マニフェストシステム(JWNET)に加入する必要があります。
加入後は、インターネット上でマニフェストの交付から処理状況の確認まで全て行えます。また、マニフェストの記載漏れや偽造を防止でき、処理終了報告の確認期限を自動通知してくれるため、法令遵守にも効果的です。
処理費用の目安
産業廃棄物の処理費用は、廃棄物の種類や処理方法、地域によって大きく異なります。適正な価格を知ることで、無駄な費用を抑えることができます。
収集運搬費と処分費
産業廃棄物の処理料金は、収集運搬費と処分費の2つに分かれています。収集運搬費は、廃棄物を回収して処理施設まで運ぶ費用で、距離や車両の大きさ、作業時間などによって決まります。処分費は、実際に廃棄物を処理する費用で、廃棄物の種類や処理方法によって大きく変わります。
処分料金の目安
主な産業廃棄物の処分料金の目安を見てみましょう。廃プラスチック類は1キログラムあたり30~80円程度、紙くずは20~60円程度、木くずは10~60円程度となっています。金属くずは0~40円程度と安価ですが、これは有価物として売却できる場合があるからです。一方、汚泥は25~50円程度、廃油は5~100円程度と幅があります。
特別管理産業廃棄物は通常の産業廃棄物より高額になります。廃石綿等は1キログラムあたり100~200円程度、感染性廃棄物は50~150円程度が相場です。これらは特別な処理設備と技術が必要なため、高額になってしまうんですね。
処理費用を抑えるコツとしては、まず廃棄物の発生量を減らすことが最も効果的です。また、適切な分別を行うことで混合廃棄物にならないようにし、複数の処理業者から見積もりを取って比較検討することも大切です。ただし、安さだけで業者を選ぶのは危険です。許可の有無や処理方法の適正性をしっかりと確認してから契約することが重要になります。

正しい処理のコツ
産業廃棄物を適正に処理するためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
業者との契約書作成
産業廃棄物の処理を委託する際には、必ず書面による委託契約書を締結しなければなりません。口約束だけでは法律違反になってしまうので注意が必要です。
委託契約書に記載すべき項目は以下になります。
・廃棄物の種類と数量
・処理方法の詳細
・処理料金と支払条件
・委託期間と更新条件
・緊急時の連絡体制
契約書では、委託する廃棄物の具体的な名称と予想される排出量を明記します。また、収集運搬から最終処分までの処理方法についても詳しく記載する必要があります。料金については、処理費用だけでなく運搬費用も含めた総額と、支払時期を明確にしておくことが大切です。
許可証の見方と確認方法
処理業者の許可証確認は適正処理のための最重要ポイントです。許可の種類や有効期限、取り扱える廃棄物の品目をしっかりとチェックしましょう。
許可証で確認すべき項目は以下になります。
・許可の種類と番号
・有効期限の確認
・取り扱い可能品目
・事業範囲の地域
・許可条件の内容
産業廃棄物処理業の許可には、収集運搬業許可と処分業許可があります。委託する業務に応じて適切な許可を持っているかを確認してください。また、委託したい廃棄物が許可品目に含まれているかも重要なチェックポイントです。許可証は定期的に更新されるため、有効期限が切れていないことも必ず確認しましょう。
最後まで処理を確認する義務
排出事業者には、委託した産業廃棄物が最終処分まで適正に処理されたことを確認する義務があります。処理業者に任せきりにせず、最後まで責任を持つことが重要です。
処理状況の確認方法は以下になります。
・マニフェストの返送確認
・処理施設の現地視察
・処理業者との定期打合せ
・処理状況報告書の確認
・緊急時の連絡体制確保
マニフェストの各票が期限内に返送されることを確認し、処理内容に問題がないかをチェックします。可能であれば年に1回程度は処理施設を視察し、適正な処理が行われているかを自分の目で確認することをお勧めします。また、処理業者との定期的な打合せを通じて、処理状況や課題を共有し、継続的な改善を図ることも大切です。
ルール違反の罰則
産業廃棄物に関する法律違反は、非常に重い罰則が科せられます。知らなかったでは済まされない厳しい処罰があることを理解しておきましょう。
不法投棄の重い処罰
不法投棄は最も重い罪で、個人には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、法人には3億円以下の罰金という重大な処罰があります。これは人生や会社経営を大きく左右する深刻な問題です。
管理票を出さない場合の罰金
マニフェストを交付せずに廃棄物を委託したり、虚偽の記載をしたりした場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。保存義務違反でも6月以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
会社の責任は最後まで続く
排出事業者責任により、処理業者に委託した後も会社の責任は続きます。委託先が不法投棄した場合、排出事業者も責任を問われ、原状回復費用の負担や刑事処分を受ける可能性があります。信頼できる業者選びが重要な理由はここにあります。
まとめ
産業廃棄物の適正処理は、環境を守り、法令を遵守するための重要な責任です。今回解説した内容を参考に、まずは自社から出るゴミの種類を確認し、信頼できる処理業者との契約を検討してみてください。適切な知識と行動で、持続可能な事業運営を実現していきましょう。分からないことがあれば、専門家や行政機関に相談することをお勧めします。
お知らせ
最後まで、読んでいただき光栄です。私たち都市環境サービスは、プラスチックリサイクルに特化した会社です。フラフ燃料の製造や代替燃料に興味がある方、リサイクルの会社で働いてみたい方は、こちらのフォームから気軽にお問合せください。よろしくお願いします。



